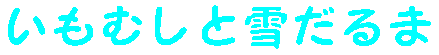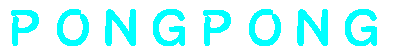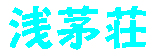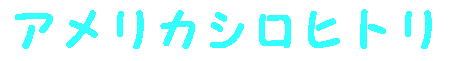えーと、おもに70年代に活躍した、栗田ひろみさんというタレントさんをご存じでしょうか。
立場としては、アイドル寄りの俳優、といったところ。
最初にお見かけした映画は、森谷司郎監督の「初めての愛」。海辺の幻想シーンに登場するだけなのですが、私はこれ一発でノックアウトされました。チョイ役だったので、ネットで見かけるフィルモグラフィーでは記載がない場合が多いみたいなんですが、この映画を知らない栗田ひろみファンなんて、認めませんからね、あたしゃ。
おいおい、大島渚監督の「夏の妹」が先だろう、などとつっこむ邦画おたくやひろみおたくの方がいらっしゃったら、ふん、君たち都会育ちのお坊ちゃんに、田舎の中学生の気持ちなんかわかってたまるか、と、いじけるしかないです。ATG映画なんて、山形の田舎じゃあ、リアルタイムで観るなんて、不可能だったんだい。
さて、その後も、森谷司郎監督の「放課後」、市村泰一監督の「ときめき」、森崎東監督の「街の灯」などの映画で、ちょっと忘れ難い存在感を披露してくれました。「氷雪の門」もあったなあ。映画は……だったが、題材と少女たちで、やっぱり泣けたなあ。
テレビでは、前後編ドラマで「伊豆の踊り子」の、踊り子・薫。
同時代に山口百恵さんの映画もありましたが、それとはまた全然ちがった、生活感の希薄な妖精のようなイメージで、私見では栗田ひろみ踊り子の勝ち。
さらに、倉本創さん脚本の連続ドラマ・「6羽のかもめ」。名作でしたね。
……その後、松尾昭典監督の「沖縄10年戦争」、神代辰巳監督の「地獄」あたりの脇役では、もうアイドルからは完全に脱皮されてましたが。
で、お話はこれからだ。
アイドル寄り、と表現したからには、当時としては当然のように、レコードも出しました。しかし、演技ができるからといって、歌もうまいとは限りません。……そうです。はっきり言って、浅田美代子さんのナマ歌に勝る破壊力だったのです。「太陽のくちづけ」。売れたんでしょうね。私も買いましたし。でも、浅田美代子さんの特にファンではなかった私が、「赤い風船」は何度も繰り返し聴いたのに対して、「太陽のくちづけ」は、もっぱらジャケットにナニしたり、ジャケットをナニしたり、ブロマイドと同様の扱いでした。そんなことでいいのか、ファンの風上にも置けんやつだ、と、お怒りの皆様、ごめんなさい。私、耳は良い方なのです。
さて、そこでレコード製作側は考えた(に、違いない)。歌が聴くに耐えないならば、次は歌ぬきで、伴奏と語りだけにしてしまえばいい。もともと役者メインの娘さんなんだから、ファンはそれで満足してくれるだろう。
……ええ、買いましたよ。「愛の奏鳴曲(ソナタ)」。
で、これがまた、悶絶するほど恥ずかしかった。レコードを聴いて、身もだえしながら、お願いだからもうやめて、と、天に向かって許しを乞うていました。
その悶絶は、息もたえだえにレコードを裏返して、B面が始まっても、まだ加速します。……今度は歌らしい。しかし、あいかわらず、歌というには、これはなにかちょっと音階というものに致命的な……。
で、そのB面のタイトルが、「蝶々と雪だるま」。いくら夢にまで見るあこがれの少女のレコードだからといって、この歌声で、おまけにバッドエンドというのは、神が許しても俺は許さない、とまあ、そんなわけで。

(8ページ)
小学生のころから、ムーミン谷に住みたくてたまりませんでした。
アニメが始まる何年も前、講談社の国際アンデルセン賞受賞シリーズが出版される以前からです。そんな以前から、ムーミンシリーズが日本で紹介されていたのか、と、疑問に思われる方も多いでしょうが、あったんですねえ。もう訳者さんの名前も挿絵画家さんの名前も忘れてしまいましたが、現在「ムーミン谷の夏まつり」として訳出されている原話を抄訳し、挿絵もヤンソンさんのオリジナルではなく、日本の挿絵画家さんが、真似して描いてました。文章の方しか、版権が買えなかったんでしょうね。でも、これちょっとヤバイんじゃないの、と、後でオリジナルを見たとき子供心に思ったほど、原画に忠実に描いてくれていたので(おいおい)、すぐにハマってしまった私は、さっそく授業中にノートにムーミンを描き始めてしまいました。
で、高学年になったとき、ピーナツ・ブックスを知りまして、瞬時にチャーリー・ブラウンに同化。でも、さすがにノートに描き始めたのはチャーリー君ではなく、スヌーピーでした。
こうして小学校を卒業するころ、ノートの上でムーミンとスヌーピーが合体してしまい、混血の(パクリとも言う)生物が誕生しており、図書館の花の図鑑にあったポンポンという名前が気に入ったので、よし、こいつ、ポンポンね、とお気軽ネーミング、現在にいたっております。
シュルツさんのピーナツの世界が、思春期以降でないと本当には理解できない世界であることは、知っている方も多いと思いますが、ヤンソンさんのムーミンの世界は、子供の心をなんとか保ち続けながら老人になって初めて、理解できるであろうと思われる世界です。死ぬまでには味わい尽くしてみたいものですね。
で、そんな至高の世界までパクれるはずもなく、PONGPONGはいつもただのほほんと生きてるだけです。
(13ページ)
さて、ここで問題です。1970年代中頃の田舎の高校で、漫画大好き少年は、どんなクラブ活動をしていたでしょう。
回答。当然漫研。ブー。残念でした。そんなものはまだ影も形もなく、少年は写真部や文芸部を渡り歩きながら、ホームルームの時間に「パンダコパンダ」がいかに革命的なアニメであるかとか、つげ義春という漫画家の文学上での位置付けとか、唐突に45分間しゃべり続けたりして、ひんしゅくをかったりしてた訳です。
さて、いろいろあってようやくすべりこんだ明大漫研。いま考えればOBには、著名なところで(私が愛読してる方だけでも)かわぐちかいじさんやらほんまりうさんやらいしかわじゅんさんやら。後輩にもプロとして現在活躍してる諸君多数。あの山田詠美さん(当時は双葉さん)などもタンクトップでうろついてくれてるという、とんでもないとこでした。
さあて、紛れ込んでしまったど素人とはいえ、丸まっこいかわいいのだけ描いててもなあ、ということで、丸まっこいなりに青年向けを試みたりしました。もともとガロ大好き少年でもあった訳ですし。でも、駄目でしたね。だって、背景なんて、やっぱり丸まっこいのしか描けないんだもの。
さて、そこで、次の問題です。上の下手くそな漫画の背景には、あの、「ペリカン・ロード」等の五十嵐浩一氏の描かれた背景が、多数存在しております。それはどことどこでしょう。もしそっち方向からいらしてくださったお客様がいらっしゃいましたら、そこだけ収集してください。、
(6ページ)
あー、もういいや。うじうじ悩んでてもしょうがない。精神年齢ここで停めちまおう、と決意したのが14歳の春。ああ、美少女たちの罪の深さよ。って、おめーが怠惰なだけだろ、俺。
何をやっても中途半端なくせに、その決意だけはなぜかヒットしてしまい、いまだにそのまんま。ピーターパン症候群の典型。14歳以下の少女たちにはガシガシ感じるくせに、成人女性には、この歳まで3回しか、恋愛感情を抱いたことがないという……。で、実際おつきあいできたのはそのうち2名だけという……。天も泣け、地も泣け。いまだ嫁も貰えず朽ちようとしている男のために。
でも、いいんだい。1度だけでも心から極楽だと思われる状態を体験してしまうと、大林監督の「時かけ」じゃないけれど、以降チョンガーまっしぐらでも、さほど寂しくはありません。別に不幸でもなんでもないです。
たとえば、あれほど恋い焦がれていたハッセルを、ボーナス1.5回分はたいて我が物にしたものの、結局ヤシカマットのほうがなんか可愛くて、生活に困るとまっさきに売ってしまうというような。って、女性の方をカメラといっしょにしてんじゃねーよ。これだから結局ふられちまうんだよ。
そんなこんなで(何がだ)、ローライフレックスF2.8Fだけは、一生ウィンドーの窓越しに熱い視線を送るだけにしておこうと、決意している私です。わざわざ決意しなくても、もうお金ないけど。