
かばうま 「……拾い画像で泣いてしまった」
たかちゃん 「おう、だれかに、にている」
くにこちゃん 「んむ、けーきをそまつにするよーなやつは、ないてとーぜんだ」
ゆうこちゃん 「……うるうるうる。なでなでなで」
[戻る]
| 12月31日 日 千のろりになって |
今年の紅白は、一見地味ながら、なかなか良かった。例によって若手の大半も演歌のベテランも似たり寄ったりで分別しにくいのだけれど(美川・小林の衣装合戦も派手には違いないが、もはやお二人が身動きできないオブジェになってしまっている)、狸ご贔屓のTOKIOは中島の姐御作の歌もあいまって意識を鼓舞してくれたし、DJ
OZMAは十二分にかぶいてくれた(あのバックのおねいさんたちが実際裸なのではないかと苦情が来たようだが、実際裸ならもっとよかった。裸だから嫌らしいとでも言うのだろうか。そうしたおすまし隠れ淫乱者の杓子定規な盲目ぶりが、昨今の合法児童ポルノの氾濫を招いているのだ)。和田の姐御は今年はノッていたし、SMAPが出るととにかく個々のオーラの色彩が爺いの眼にもひとつひとつ際立って見えて、ほっとする。
『千の風になって』を秋川雅史さんが歌っていた。もとになった作者不詳の詩は、なぜかアメリカで同時多発テロの追悼式で朗読されたとか、ハワード・ホークスの葬儀で俳優のジョン・ウェインが朗読したとか、マリリン・モンローの25回忌にも朗読されたとか、種々のエピソードがあるのだけれど、不思議である。根本的に、キリスト教的世界観に矛盾しているからだ。あの世界観は、むしろ原始的祖霊信仰に近いものだし、また仏教にも通底している。アメリカ先住民の歌が元ネタだという話もあるので、それが正しいのか。
ちなみに全世界で2〜3人の方々にネタバレしてしまうが、とうとう歳末まで終わらず新年に完結予定のクリスマスたかちゃん物は、今夜気づいてみれば、あの歌にインスパイアされたのかもしれない。
ところで、謎のひとこと。
あなたが誰かを好きになるか嫌いになるかはあなたの自由ですが、他の誰かがあなたを好きになるか嫌いになるかは、残念ながらあなたの自由にはなりません。ちなみにあれを読んで、親近感を覚えてしまう方も多いのではないかと、私には思われます。
なにはともあれ、日々の繰り言につき合ってくださっている皆様、どうぞ、よいお年を。
| 12月30日 土 ♪ わたしは〜ひとり〜かた〜すみで〜 ♪ |
ステーキ・ハウスは許されないが、100円回転寿司なら許されるのではないか――ああ、惰弱な私。などと頭を掻きつつ、コインランドリーで乾燥機が回っている間に、近所のかっぱ寿司に行った。狸の周囲ではなぜか「おいしくない」という意見が多いのだが、狸としては実は下手な普通の寿司屋より好きである。といって、ここ何年かまともな寿司屋に入った記憶など、ないのだけれど。
で、るんるんと自動ドアをくぐり、あっと驚いた。一人がけのカウンターが無くなっている。いや、良く見れば奥の一列だけが、かろうじて残っている。前回までは、その大型店舗に三列六面あった回転部分の半分が一人がけ、残り半分がファミリー席の構造だった。それがいきなり、一対五の苦戦を強いられている。 これは明らかにひとりもん差別ではないのか。などとつむじを曲げつつ、しかし縁側もアブリ牡蠣もしゃけもたいへん美味しゅうございました。
考えてみれば、ファミレスなどもとから一人席はほとんどない。駅前の松屋でさえ、ファミリー席を置く今日この頃だ。ひとりサミしくぽつねんと生きているほうが、きっとまちがいなのである。ふん。いいもんいいもん。どーせみんな死ぬときゃひとりだもん。などと拗ねつつ、待てよ、近頃なんだかまた「みんなでどーっといっしょになんかまたさあ逝け!」的な風潮が内閣や文科省に増えつつあるのは、やはり時代の流れなのかしら、などと強迫観念にも囚われがちな貧しい狸であった、まる、と。
| 12月29日 金 たかちゃんたちの風 |
年末年始は仕事がなく、そして今年は遊ぶ金もいっさいない。図書館は休みだし、徘徊すると風邪など拾ってしまいまた病院代がかかる恐れもあるので、主に売り残した本や売れないビデオ類、めっきり減ってしまった新規録画希望物件、そしてたかちゃんなどが友である。本日はたかちゃんたちと一日中遊んだ。長期シリーズ物だからいちいち背景説明などしないので、続きを読んでくれる方もほとんどいなくなってしまい、自分にとって悲しき玩具のように思われてしまう時もあるのだが、たかちゃんたちが無邪気に芸をしてくれる限り、たったひとりの読者にでも、それを真摯に伝え続けたいと思う。自分はたかちゃんたちの挙動から、自分のいる世界を省みさせてもらっているのだ。たかちゃんたちは、哲学的アウフヘーベンの先から、遊びに来てくれているに違いないのである。
姉から援助が届いた。食料も、金銭的援助も。嬉しさと共に、それが今回は本当にギリギリの援助でステーキ・ハウスに走るなど許されない現状に、我が人生最大のビンボを感じ、いささかめげそうにもなる。
しかしたかちゃんたちは、そんな懊悩にいささかの正当性もないことを曝いてくれると同時に、なんら劣ってもいないことを、笑いながら謳ってくれる。
風立ちぬ、いざ生きめやも。
| 12月28日 木 赤子《せきし》を憂う |
などと現人神のごとく大袈裟なタイトルだが、いつもの狸愚痴です。
今年はクリスマスにも鳥食わなかったなあ、と思い当たり、モス・バーガーに行ってチキンなど奮発した。オニオン・リング共々、ケンタよりも好物なのである。本当はロッテリアのリブサンドとチキンだと個人的にもっと贅沢気分になるのだが、自分の今のテリトリーでは、神保町まで遊びに出ないと店がないし、今年の歳末は(そして新年もとりあえず確実に)その余裕がない。電車賃だけで数百円かかる。そのぶんはできるだけ食費や本に回したい。
モスはマックより高くつくせいか、この街では高校生型の生ゴミなどに比較的遭遇しにくいのだけれど、運悪く、若奥様型の生ゴミが隣に座ってしまった。後からベビーカーを押して来店、一人がけテーブルに陣取ったのだが、そのベビーカーを隣に配置するため横のテーブルと椅子をごとごとと移動し、その際狸の椅子に何度かぶつかった。しかし「すみません」のひと言どころか、会釈すらない。それからテーブルの上に携帯を放り出し、食っている間に何度も何度も着信音が鳴り、そのたんびにメールをポチポチしているが、マナーモードとかに切り替える気はまったくないらしく、さらに何度も何度も着信音が鳴る。まあ当節の世間は、娘型の生ゴミがそのまま育ってしまったヤンママ型生ゴミも日々増殖しているので、今さら気にしたくもないし、ベビーカーの赤ちゃんがきゃっきゃとごきげんなので、そちらに懐柔されてしまい、黙って食べていたのだけれど。赤ん坊というやつは、成長に伴って親以外の外の社会を客観的に相対化する能力が生じるから、必ずしも親同様に腐ってしまうとは限らない。しかしどうも生ゴミというやつは、手近な物に黴菌を増殖させたがるので、ああかわゆい赤ちゃん、ぜめて丈夫な抗体を自分の体内に育てておくれと、祈るばかりである。
状況はずいぶん違うとはいえ、以前に記した電車の中で堂々と化粧直しをしている女性達、あれも実は根っこが同じだと思うのですね。自分が関係を認知した人間以外は書き割りと同じ、そう顔に書いてある。
| 12月27日 水 へるん幻視行 |
無数のおたく要素も老いと共に曖昧化しつつある(?)自分だが、最後まで残りそうな興味対象として、小泉八雲=ラフカディオ・ハーンがいる。ご多分に漏れず子供の頃から『雪女』の哀切やエッセイ的小品の叙情に親しんでいたし、中学高校で原文なども読まされたし、長じて平井呈一先生の訳に出会ってからは、目から鱗が落ちたようにその世界に引き込まれた。そしてその作者そのものに対する評論や評伝を読む内、なんというか、そのキリスト教的西洋世界に相容れなかった寄る辺なき孤独な少年の青春放浪、そんなものがこの日本という国の明治、いや、すでに失われつつあった江戸期以前の日本人の情緒に帰結してくれたことに、心底感謝・同調できた。結句文明というものは母性=無償の愛を顧みずに突き進むものであり、土俗こそが野卑も歪みも含めて母性に基づく。
先日金もないのに購入した、 宇治谷順原作ほんまりう作画の『へるん幻視行』、なんとはなしにこなれが良くないものの(なんて生意気に、ほんまりう大先輩ごめんなさい)、かつて読んだ八雲ネタのミステリーやホラーの中では、最も納得できる出来だった。完全な虚構ながら、八雲の行動や言葉に、精神的に「さもあらん」と同調できる。八雲の作品を基にした原作のひねり具合もいい。
ただ気になったのは、いつもの劇画タッチでなく文芸調(?)の細い線で、人物の頭身まで縮めて描いたのは、題材が民話的なものだからなのだろうか。これは誤りだったのではないか。いつものちょっと不器用だが人間くさい劇画タッチほんまりう流で、良かったのではないか。ああ、生意気にごめんなさいごめんなさい。
| 12月26日 火 バカは死ななきゃ治らない |
とは常々思っていたものの、自分のバカや他の個人のバカは、まあバカ同士でなんとか折り合い付けるとして――なんということだ、この国の司直まで、あいかわらずバカが多いのであった。
先だって、名張毒ぶどう酒事件でようやく再審開始が決定され、おうおう、この国もようやくバカから一歩お利口に近づいて行くのかと安堵していたら、いきなりの決定取り消しである。思わず「あが!?」と、下顎が太ももまで落っこちた。
『◇名張毒ぶどう酒事件 再審取り消しに「戦いは続く」弁護団
開きかけた再審への狭き門が、また閉じてしまった――。5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、名古屋高裁は26日、検察側の異議を認め、再審開始決定を取り消した。悪夢を見たかのように「不当決定」の幕を掲げる弁護団。その光景を見た支援者たちは声をなくした。弁護側は特別抗告するとみられ、舞台は最高裁へと移る。事件発生から既に45年が経過。拘置所で満80歳を迎えた奥西勝死刑囚は、年齢的にも「これが最後の機会」と願いを託している。残された時間は余りに少ない。【岡崎大輔、米川直己、鈴木顕】
午前10時過ぎ、弁護団の1人が名古屋高裁正面玄関に出てきた。掲げられたのは「不当決定」の幕。集まった約130人の支援者らの間から「なぜ」と悲鳴が上がった。
泣き崩れる支援者らを前に、鈴木泉弁護団長は「再審請求を棄却する」と名古屋高裁の決定を読み上げ、言葉をつまらせた。その後、右手を震わせながら、力を振り絞るように「これまで再審開始決定に対する検察の異議をことごとくはね返してきて、裁判所は(我々の主張を)十分に分かっていたはずである。戦いはまだまだ続くが、弁護団としては、奥西さんと固く抱き合い、握手できる日が来るまで全力を尽くしたい」と訴えた。
奈良県山添村議で奥西死刑囚の親戚にあたる奥谷和夫さんは「不当決定としか言いようがない。司法の判断に、がく然とした」と厳しい表情。特別面会人の稲生昌三さん(67)は「人の命をもてあそんでいる。怒りでいっぱいです。再審制度は救済のためにあるはず。決定は人道に反する」と、目に涙を浮かべた。
◇「正しい判断下された」…被害者の夫
事件の舞台となった三重県名張市葛尾地区の住民からは安堵(あんど)の声が漏れた。
事件で妻を亡くした奥西楢雄さん(81)は「正しい判断が下された。45年前にあれだけ徹底して捜査されたので、当初から(今回の決定を)確信していた」。弁護団が特別抗告する可能性が高いことについて「(結果は)同じこと」と話した。事件で妹を亡くした坂峰敏一さん(79)は「45年は長かったが、再審が取り消され、良かった。期待通りの決定で、(騒ぎも)治まるだろう」と安心した様子だ。
一方、名張市で再審開始を求める署名活動をしてきた支援組織「名張市奥西さんを支援する会」の赤瀬川勝彦・代表幹事(59)はこの日、会員らと同高裁近くで集会を開いた。「まったく不当な決定で、信じられない。怒りで体が震えている。こんな決定が出るようでは、刑事裁判の再審制度は絵に描いた餅になってしまう」と批判。「最高裁では今回の決定が取り消されることを期待している」と話した。【熊谷豪、小槌大介、渕脇直樹】
◇「再審制度形がい化」
名張毒ぶどう酒事件をテーマにした著書があるジャーナリスト、江川紹子さんの話 科学的な鑑定に対し、科学的に反論する主張を並べて判断するのではなく、とにかく「ダメだ」と門前払いしたようなものだ。自白さえあれば、真犯人が特定されない限り再審はしないということか。警察と裁判所は間違いを犯さないという宣言であり、再審制度を形がい化させる決定だ。他の裁判に与える影響も大きく、裁判に対する国民の不信感を招くものだ。 最終更新:12月26日17時46分配信 毎日新聞』。
以前、砒素カレー事件や三浦事件の時も記したが、自分だって真実など何も解らないのである。ただ、どんなバカにでも判る事実、それは『信頼できる物的証拠がない』、それだけの事実だ。何度も言うように、自分は立派な死刑肯定論者である。報復殺人の共犯者である。だからこそ、死んだらその鬼畜と同じ地獄に堕ちても本望、そんな殺人にしか加担したくない。情況証拠や心証、信憑性に疑いの残る自白、司直側の面子、そんなタワけた理由で、このぶよんとしてしまりのない不潔な手を、さらに汚すわけには行かないのだ。それでは無差別殺人犯と、なんら変わりがない。
つまり狸としては、今回の名古屋高裁による殺人計画に、断じて与する意思がない。そして45年前の被害者の遺族の方々にも重々敬意を払いつつ、物証なき私刑はただの無差別殺人である、そう言わざるをえない。
| 12月25日 月 クリスマス・キャロル |
ケーブルで、パトリック・スチュアートがスクルージを演じる『クリスマス・キャロル』を観た。『スター・トレック』の最近のシリーズも『X−MEN』も観ていない自分にとっては、スチュアート氏はあくまで英国風の渋い脇役、クセのある悪役が得意、といったイメージなので、いかにもスクルージなどハマりそうで、月初めから期待していた。噂によれば、舞台の一人芝居で何度も演じ、定評のある持ち役らしい。
さて本編は――ううむ、演出があまりにも大人で、あくまで童話としての原作に幼少時からぞっこんの狸としては、少々首をひねった。人物造形がリアルなのはいい。大人が大人としてしっかり描かれているのもいい。しかしやはり、基調としての童話感(?)、つまりその物語の世界観を現実より一皮剥いた視線から語り聴かせる、そんな風味が足りなかった。日本で公開あるいはビデオ発売あるいはテレビ放映された『クリスマス・キャロル』はほとんど観たが、いずれも一長一短な中、総合的に1984年のジョージ・C・スコット主演のTVドラマが、最も原作の風合いというか風格を、色濃く再現していたように思う。けして原作に忠実というわけではないのだけれど、要は視線の置き所の問題なのである。
ともあれディケンズの原作自体がすでに至高なので、今年も読み返してみようと思う。出版当時、ライバル作家のサッカレーが「こうした作品が書けたら、全財産をなげうっても惜しくない」と言ったそうだが、実際無一文の狸としても、「こうした作品が書けたら、直後に死んでも惜しくはない」と、本心から思える作品だ。厳しい冬を暖める童話としても、ゴシック・ホラーとしても、文学としてもエンタメとしても、とにかく良くできている。そして何より、サッカレーがこうも言ったという賛辞に、激しくこくこくと頷いてしまう。「こうした書物に対する批判的意見に、私はいっさい聴く耳を持たない。私にとってこの作品は国家的利益であり、誰にとっても個人的親切行為と思われるからである」。
| 12月24日 日 泣いたらアカン |

かばうま 「……拾い画像で泣いてしまった」
たかちゃん 「おう、だれかに、にている」
くにこちゃん 「んむ、けーきをそまつにするよーなやつは、ないてとーぜんだ」
ゆうこちゃん 「……うるうるうる。なでなでなで」
| 12月23日 土 即席ラーメン |
本日の朝日新聞の土曜版、『サザエさんをさがして』で、インスタント・ラーメンの話題が取り上げられていた。簡略な開発秘話やその後の歴史、つまり気軽な昭和レトロのコラムだけれど、冒頭に、10年前のペルー大使館ゲリラ占拠事件中のエピソードがあり、少々心がうずいた。赤十字が差し入れたカップ麺を、『20歳の女性ゲリラが「こんなおいしいものを食べたことがない。家族にも食べさせたい」と、手投げ弾を入れたリュックに入るだけ詰めこんだ』。人質の1等書記官・小倉英敬氏の話とあるから、事実なのだろう。
作者は忘れてしまったが、昔、東南アジアの放浪記を読んでいて、似たような話に出会ったことがある。その青年が、国境近くの山中で、夜食に具もない袋ラーメンを煮ていると、国境警備員が回ってきた。その奇妙な食物に興味を覚えたらしいので、懐柔のためもあり食べてもらうと、「お前達は毎日こんなうまいものを食っているのか!」と、心底羨ましがられたと言うのである。
笑っても憐れんでもいけないだろう。自分が幼時、袋ラーメンを生まれて初めて近所の友達の家で食べた時も、実はそう思った。山形にはまだ元祖『チキンラーメン』が、いや、他のメジャーな袋ラーメンもほとんど出回っておらず、当時から総合食品卸会社として地方まで根をはっていた、『国分』ブランドだったと記憶している。
朝日新聞のコラムには、坊主頭の小学生が、木造校舎で即席ラーメンを作っている写真もあり、『「ヒエめし」弁当を食べていた小中学校に贈られ給食となる即席ラーメン=65年7月、岩手県岩手町で』とある。東京オリンピックの翌年でも、地方はそんなもんだったのですね。数えてみたらどんぶりは24個並んでいるので、生徒24人の分校か。コメにしてやれよ、とも思うのだが、まあなんかいろいろ、歴史上の都合があるのだろう。また「ヒエのほうが当時の袋ラーメンより、まだ栄養あるんじゃないの?」とも思うが、それもまた現在の価値観である。
ちなみに現在では、袋ラーメンにもビタミンやミネラルがしこたま添加されており、当時のように「即席ラーメンばかり食って脚気になる」、そんな心配はなさそうだ。そして空腹時に啜る狸の好物『明星チャルメラ』は、あいかわらず、とても美味だ。
昨夜は某投稿板でクリスマスネタのとんでもねー愚作に出会ってしまい、他の方の読んでみたい新作もあったのだが、発作的に自分なりのクリスマスネタを着想、徹夜で第一話を打って、朝方投稿してしまった。その愚作とは、背徳的で淫靡で暴力的だから愚作、と言うのではない。幼い少女と兄が受ける児童虐待(性的虐待含む)、そうして歪んでしまった兄妹がサンタや周囲の人物を惨殺、といった一見問題作っぽいキャッチーな趣向にもかかわらず、人間の根源的な『痛み』など何も汲み取れない、明らかに精神年齢14歳未満の『問題作』だったのである。そんなことをくどくど感想に入れても通じるとは思われない前歴の作者だったので、思わずその直上になんでもいいから自分のネタカブリ物件を配置し、大人げない嫌がらせに走ってしまったのである。で、今し方また覗いてみたら、その問題物件は消滅していた。目標撃沈。児童虐待や小児姦を実行する奴は、まあ事情にかかわらず最終的に来世で修行させるしかないが、それを客観的に描こうとする者は、殴打され犯される立場の痛みとともに、なぜジル・ド・レーが断末魔の幼児に射精するとき自らも泣いていたのか、想像できなければならない。
――ううむ。自分もやっぱり精神年齢14歳、精神厨房だよなあ。しかしこれで、自分の前作も終わっていないのに、その発作的クリスマス物件を先に完結する義務が生じてしまった。私の馬鹿。
| 12月22日 金 太鼓腹の冬 |
『21日公表された平成18年度学校保健統計調査で、子供の「肥満化」に歯止めが掛からない現状が示された。食生活の乱れや食材の変化、運動不足など理由はいろいろ挙げられ、国も自治体も対策を講じてきたが、肥満児、肥満傾向児童は今年度も増えた。特に、なぜか東北地方で肥満傾向が強くうかがえるなど「東高西低」がくっきり。メタボリック(内臓脂肪型肥満)症候群の時代、「子供の肥満」対策も急務だ。
調査結果で年齢別の肥満児の出現率を見ると、男子は、5歳で2.57%、7歳で6.22%と増え始め、9歳で10.83%と1割を突破。ピークは15歳の13.52%で、9〜17歳で10%超の状態が続く。女子で10%を超えるのは12歳の10.16%と15歳の10.06%で、男子ほどの肥満化はみられないが「男女とも昭和52年度以降、一貫して上昇傾向が続いている」(文科省)。
地域別でも大きな差が出た。男子の15歳での出現率を都道府県別に見ると、全国で最も低いのは埼玉の8.71%。次いで静岡の9.13%で、10%を割り込んだのは群馬(9.14%)と熊本(9.91%)を含め4県だけだ。
一方、最も高いのは秋田の21.43%で、5人に1人に肥満傾向が見られる。47都道府県のうち、15歳の肥満傾向が15%を上回ったのは北海道、青森、岩手、秋田、山形、福島、栃木、徳島の8道県で、「東高西低」ぶりが鮮明に表れた。
理由について文科省担当者は「正確なことは分からない」と首をひねっている。
子供の肥満の割合が全国トップクラスの秋田県。県保健体育課では「秋田の子供は身長も体重も平均を上回り体格がいい。正確な分析はできていないが、それが肥満児の多さにもつながっているではないか」と話す。県は平成13年に策定した「健康秋田21計画」で肥満児を7%に抑える目標を掲げているが、達成は厳しいという。
秋田市の小児科医で、市教委と連携しながら小学生の体格について調べている大野忠さん(73)は「東北の肥満傾向は、やはり冬の運動不足が原因ではないか」と分析する。大野さんによると、秋田市内の子供は、冬を経た春の調査結果に比べ、秋の調査結果の方が体格がスリムになる傾向があるという。
あきた病院(秋田県由利本荘市)小児科の白崎和也医長は「秋田では都市部より郡部で子供の肥満が多い。遺伝的な要因もあるが、学校が遠くて親が車で送迎することが多いことも運動不足の一因ではないか」と話す。
日本食育協会の鈴木雅子理事(福山平成大学客員教授)は「日本では食事の内容や生活環境の均一化が進んでおり、東高西低の原因を断定するのは難しい」と不思議がる。その上で、「寒い地域では外に出て遊ぶより家の中にいる時間が長くなる。当然食べ物を口にする機会は増える」と推測する。
女子より男子に肥満が多いことについては「女の子の場合、親も本人も幼稚園の時から容姿を気にしてダイエットする。男の子が容姿を気にし始めるのは小学校高学年と遅いため」とみている。
鈴木理事は「最近の子供は動きたがらず、動物性脂肪と糖質が高くて、軟らかいものを好む。対策には具体的な食事内容と運動量に関する詳細な調査が必要だ」と指摘している。』(SankeiWEB 生活・健康 『なぜ? 東北の子供に肥満傾向 寒さで運動不足か』より)。
もと北国の肥満児として重々思い当たることは多いのだが、昔は『学校が遠くて親が車で送迎する』などという贅沢な家庭はほとんどなかったので、肥満児は肥満児なりに往復3キロの雪道を毎日歩いていたわけだし、餓鬼のことゆえ多少体調がおかしくても仲間遊び優先で、雪の校庭を駆け回ったり城跡の土手を転げ落ちたりしていたのだから、そう不健康ではなかったような気がする。アンコ型のおすもうさんだって人気ありましたしね。現在の北国では、寒冷地であればあるほど戸口から戸口を車で移動してしまう場合が多く、確かに子供も例外ではない。そして家の造りも、昔の農家のように周回できる長い廊下やよじ登って遊べる屋根などなかろうから、いきおい一室でのたのたしていることになるのだろう。
しかしまあ今も昔も、『男の子が容姿を気にし始めるのは小学校高学年と遅い』とはいえ、いずれ女子の目が気になり出すのは必至で、そのとき走り込みでもやれば、成長期ゆえすぐに痩せる。それすらできなくなりつつあるとすれば、きっとイロケが不足しているのだ。いや、イロケが周囲の女子でなく、おたく的仮想物件に向かってしまうのか。
ともあれ、もはや女性の目を気にする余裕もなくビンボ太りに身を任せている中年狸としては、全世代に同類が増えて、デブ同士が世代を越えて仲良く腹鼓や赤ヘソを競い合えるような世の中が訪れれば、それはそれで幸せだろうと思う。これ以上富裕国の平均寿命など増やすのは、とても地球に優しくない気がするし。
| 12月21日 木 罪と罰 |
子供の頃から江戸物――テレビでやってる時代劇のみならず、雑誌『太陽』の江戸特集や浮世絵など好んで観ていた自分にとって、無論その封建時代の社会問題も重々察しつつ、それでもなお明治以降の現代に繋がるいわゆる『文明開化』に疑問を抱いてしまうのは、やはり人と人との連環の在り方――人権とやらの主体をどこに置くか、である。
などと堅っ苦しい言い方はさておいて、中学高校と愛読していた岡本綺堂の半七捕物帳シリーズを時折読み返していると、当時は深く考えていなかったおそろしく直截な『罪と罰』の観念に、思わず襟を正してしまったりもするのだ。
昨夜寝床で読んでいて「うひゃあ」と驚愕してしまった(つまり昔読んだのにすっかりボケて忘れてしまっていた)そのシリーズの一編を、そっくりそのまま青空文庫からコピペさせていただこうと思う。
半七捕物帳 〜小女郎狐〜
岡本綺堂
--------------------------------------------------------
【テキスト中に現れる記号について】
《》:ルビ
(例)手心《てごころ》
|:ルビの付く文字列の始まりを特定する記号
(例)大岡|捌《さば》きのように
[#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
(数字は、JIS X 0213の面区点番号、または底本のページと行数)
(例)※[#「しんにょう+(山/而)」、第4水準2-89-92]
--------------------------------------------------------
一
なにかのことから大岡政談の話が出たときに、半七老人は云った。
「江戸時代には定まった刑法がなかったように考えている人もあるようですが、それは間違いですよ。いくら其の時代だからといって、芝居や講釈でする大岡|捌《さば》きのように、なんでも裁判官の手心《てごころ》ひとつで決められてしまっちゃあ堪まりません。勿論、多少は係りの奉行の手心もありますけれども、奉行所には一定の目安書《めやすがき》というものがあって、すべてそれに拠って裁判を下《くだ》したもので、奉行の一料簡で殺すべきものを生かすなんて自分勝手のことは、なかなか出来ないような仕組みになっていたんです。それは昔も今も同じことです。しかしその目安書というのが今日の刑法などに比べると余ほど大づかみに出来ていますから、なにか毛色の変った不思議な事件が出来《しゅったい》すると、目安書だけでは見当が付かなくなって、どんな捌きを下していいのか、係りの役人どもはみんな頭を痛めてしまうんです。そこらが名奉行とぼんくら[#「ぼんくら」に傍点]の岐《わか》れるところで、大岡越前守や根岸肥前守はそういう難問題をうまく切り捌いたのでしょう。江戸の町奉行所さえその通りですから、まして諸国の代官所……それは諸国にある徳川の領地、俗に天領というところを支配しているので、その土地の出来事は皆この代官所で裁判することになっていたんです。……そこでは、とてもむずかしい捌きなどは出来ないし、又うっかりした捌き方をして、後日《ごにち》に譴責《けんせき》をうけるようなことがあっても困るので、少し手にあまるような事件には自分の意見書を添えて『何々の仕置可申付哉、御伺』といって、江戸の方までわざわざ問い合わせて来る。それに対して、江戸の奉行所から返事をやるのを『御指図書《おさしずがき》』といいます。つまり先方の意見に対して、その通りとか、再吟味とか、あるいは奉行所の意見を書き加えてやるとかするので、それに因って初めて代官所の裁判が落着《らくちゃく》するんです。死罪のような重い仕置は勿論のこと、多寡が追放か棒敲《ぼうたた》きぐらいの軽い仕置でも、その事件の性質に因っては江戸まで一々伺いを立てたもので、くどくも云う通り、いくらその時代だからといって、人間ひとりに裁判を下すということは決して容易に決められるものではなかったのです。
いや、飛んだ前置が長くなりましたが、その代官所からわざわざ伺いを立てて来るほどのものは、いずれも何か毛色の少し変った事件ですから、江戸の奉行所でも後日の参考のために『御仕置例書《おしおきれいがき》』という帳面に書き留めて置くことになっていました。勿論、これは係りのほかに他見を許されないことになっているんですが、わたくしを贔屓《ひいき》にしてくれる吟味与力から貸して貰って、ちょっと珍しいと思うのだけを少し書きぬいて置きました。そうそう、そのなかに小女郎狐という変った事件がありましたから、お話し申しましょう。この事件は『御仕置例書』の日付けによると寛延元年九月とありますから、今からざっと百七十何年前、かの忠臣蔵の浄瑠璃が初めて世に出た年のことですから、ずいぶん遠い昔のことですよ」
「御仕置例書」にはいずれも国名と村名とを記《しる》してあるだけで、今日のように郡名を記してないので、ちょっと調べるのに面倒であるばかりでなく、その当時とは村の名の変っているのもあるので、その方角を見定めるのはいよいよ困難であるが、ともかくも「御仕置例書」には下総国《しもうさのくに》新石下村《しんいししたむら》とある。寛延元年九月十三日夜の亥《い》の刻(午後十時)から夜明けまでのあいだに、五人の若い男が即死、二人が半死半生という事件が出来《しゅったい》したので、村中は大騒ぎになった。
場所は庄屋茂右衛門が持ちの猪番《ししばん》小屋で、そこには下男の七助というのが住んでいた。猪番小屋といえば何処でも小さい狭いものであるが、これはともかくも人の住めるだけには出来ていたらしく、番人の七助は夜も昼もそこを自分の家にして、昼は野良《のら》かせぎの手伝いに日を暮らし、夜はそこで猪の番をしていた。七助はまだ十九の若い者であるので、村の若い者たちはそこをいい遊び場所にして、毎晩のように寄りあつまって馬鹿話に夜をふかすばかりか、悪い手慰みなどもするという噂であったが、主人の茂右衛門は別に咎めもしないで捨てて置いた。
事件の起った晩にあつまったのは、佐兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門、甚太郎、権十の六人で、今夜は後《のち》の月見というので、何処からか酒や下物《さかな》を持ち込んで来て、宵から飲んで騒いでいた。
「猪番なんぞはどうでもいい。猪の奴め、この騒ぎにおっ魂消《たまげ》て滅多に出て来るもんじゃあねえ」
こんなことを云って、番人の七助をはじめ、六人の者もさんざんにしゃべって、騒いで、いい心持に酔い倒れてしまった。畑中の一軒家ではあるが、かれらの笑い騒ぐ声が亥の刻頃まで遠くきこえたのを村の者は知っていた。しかしその夜が明けても猪番小屋の戸は明かなかった。いつも早起きの七助が今朝は起きて来ないのを怪しんで、庄屋の家の者が見まわりに来ると、表の戸は閉め切ってあって、戸の隙き間から眼にしみるような煙りが流れ出していた。いよいよおかしく思って戸をあけると、狭い小屋の中から薄黒い煙りが一度にどっと噴き出して来て、一時は眼口《めくち》もあけられない程であった。もともと狭い小屋のなかに、大の男が七人も重なり合って倒れているのであるから、殆ど足の踏みどころもない。それを一々呼び起すと、かすかに返事をしたのは甚太郎と権十の二人だけで、番人の七助と佐兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門の五人はもう息が絶えていた。ほかの二人も半死半生であった。
小屋|主《ぬし》の茂右衛門は勿論、村じゅうの者が駈けつけていろいろ介抱したが、どうにかこうにか正気づいたのは、やはり甚太郎と権十の二人だけで、ほかの五人はどうしても生きなかった。生き返った二人の話によると、かれらは正体もなく酔い倒れてしまったので、何事も知らない。夢うつつのように何だかむやみに息苦しくなったと思いながらも、身動きすることも出来なかったというのである。始めは何か食い物の毒あたりではないかという説もあったが、だんだん調べてみると、炉のなかには松葉を焚いたらしい灰がうず高く積っている。焼け残った青い松葉もそこらに散っている。かれらは夜寒《よさむ》を凌ぐために焚き火をして、その煙りに窒息したのではないかともおもわれたが、ふたりは松葉などを燃やした覚えはないと云い張っていた。夜がふけて雨戸をしめたのは知っているが、炉のなかに木の葉など炙《く》べたことはない、第一この小屋のなかには青い松葉などを積み込んであるのを見たことがないと云った。
しかしここの炉に松葉をくべた証拠はありありと残っている。しかもおびただしい松葉を積みくべたのは、そのうず高い灰を見ても知られた。更に調べてみると、松葉ばかりでなく、青唐辛《あおとうがらし》をいぶした形跡もある。七人の男が正体もなく寝入っている隙をうかがって、何者かがこの小屋に忍び込んで、青松葉や青唐辛のたぐいを炉に積みくべて彼等をいぶし責めに責め殺したのであろう。狐つきの病人から狐を追い出そうとして、病人をむごたらしい松葉いぶしにして、とうとうそれを責め殺してしまったというような話は、江戸にも田舎にもときどきに伝えられるが、これは単に酔い倒れている男七人を松葉いぶしにしたのである。あまりの怖ろしさに人々も顔を見あわせた。
場所が猪番の小屋であるから、それが盗みの目的でないことは判り切っていた。さりとて七人が七人、揃って人の恨みを受けそうもない。勿論、そのなかには何の罪もなく傍杖《そばづえ》の災難をうけた者もあるかも知れないと、庄屋の茂右衛門が先に立っていろいろに詮議をしたが、差しあたり是れという心あたりも見いだされなかった。そのうちに誰が云い出すともなく、それは狐の仕業《しわざ》であるという噂が伝えられた。
昔からこの土地には、小女郎狐というのが棲んでいて、いろいろの不思議をみせると云い伝えられている。ある時には美しい女に化けて往来の人をたぶらかすこともある。美少年にも化ける、大入道にも化ける。あるときには立派な大名行列を見せる。源平|屋島《やしま》の合戦をみせる。こういう神通力《じんつうりき》をもっている狐であるから、土地の者も「小女郎さん」と畏《おそ》れうやまって、決して彼女に対して危害を加えようとする者もなかった。ところが、今から五、六日ほど前に、この畑で猪を捕るために掘ってある陥穽《おとしあな》のなかに小さい狐が一匹落ちて迷っているのを発見して、番人の七助とあたかもそこに来あわせた佐兵衛、次郎兵衛、弥五郎、六右衛門との五人がすぐにその狐の児を生け捕って、いたずら半分に松葉いぶしにして責め殺したことがある。おそらく彼《か》の小女郎狐の眷族《けんぞく》であって、その復讐のために彼等もまた松葉いぶしのむごたらしい死を遂げたのであろう。その証拠には直接に手をくだした五人は命をとられて、無関係の二人は幸いに助かった。それらの事情から考えると、どうしてもこれは人間の仕業でなく、たしかに狐の祟《たた》りに相違ないという説がだんだん有力になって来た。
役人の検視も一応済んで、五人の死骸は村の高巌寺に葬られた。ここらの葬式は夜であったが、その宵に無数の狐火が寺のうしろの丘の上に乱れて飛んでいるのを見た者があった。
二
「どうも朝夕はめっきり冷たくなりました」
八州廻りの目あかしの中でも古狸の名を取っている常陸《ひたち》屋の長次郎が代官屋敷の門をくぐって、代官の手附《てつき》の宮坂市五郎に逢った。長次郎はその頃もう六十に近い男で、絵にかいた高僧のように白い眉を長く伸ばしていた。
「やあ、常陸屋か。だんだんと日が詰まって来るな」と、市五郎は玄関に近い小座敷で彼と向い合った。
「なにかとお忙がしいでございましょうね」と、長次郎は会釈《えしゃく》して筒提げの煙草入れを取り出した。「早速でございますが、何か新石下の方に御検視があったそうで……。わたくしは親類に不幸がございまして、きのうまで土地を留守にして居りましたもんですから、一向に様子が判りませんのでございますが……」
「検視は八州の方で取り扱ったので、わたしもよくは知らないが、その顛末《てんまつ》だけは詳《くわ》しく知っている。新石下の百姓どもが五人死んで、ふたりは生き返った」
松葉いぶしの一件を市五郎からくわしく説明されて、長次郎は顔をしかめた。かれは煙草を一服吸ってしまって、しずかに云い出した。
「なんだか妙なお話ですね。小女郎狐ということはわたくしも前から聞いては居りますが、その狐がかたき討に五人の男を殺すなんて、今の世の中にゃあちっと受け取れませんね。それこそ眉毛に唾《つば》ですよ。あなたのお考えはいかがです」
「わたしにも別に考えはない」と、市五郎は困ったような顔をしていた。「ほかに詮議のしようもないらしいので、まずそれに決めてしまったのだが、煙《けむ》にむせて死んだには相違ない。狐の祟りはどうだか知らないが、松葉いぶしはほんとうだ。生き残った二人はそんな覚えがないというけれども、自分たちが火を焚いたのを忘れているのだろう。なにしろ正体もないほどに酔っていたというからしようがあるまい」
「下手人《げしゅにん》はあるじゃありませんか」と、長次郎は笑った。「小女郎狐という立派な下手人があるんでしょう」
市五郎は苦笑《にがわら》いをしていた。
「ねえ、宮坂さん」と、長次郎はひと膝すすめた。「及ばずながらわたくしがその小女郎狐を探索しようじゃございませんか。狐はきっとどっかにいますよ」
「むむ。こっちが古狸で、相手が狐、一つ穴だからな」
「洒落《しゃれ》ちゃあいけません。真剣ですよ。ともかくも古狸の狐狩というところで、常陸屋の働きをお目にかけようじゃありませんか。いずれ又伺いますが、御代官様にもよろしくお願い申します」
市五郎に別れて出て、長次郎はその足で高巌寺へゆくと、そこらに群がって飛ぶ赤とんぼうの羽がうららかな秋の日に光って、門の中にはゆうべの風に吹きよせられたいろいろの落葉が、玄関に通う石甃《いしだたみ》を一面にうずめていた。庫裏《くり》をのぞくと、寺男の銀蔵おやじが薄暗い土間で枯れ枝をたばねていた。
「おい、忙がしいかね」と、長次郎は声をかけた。「焚き物はたくさん仕込んで置くがいい。もう直き筑波《つくば》が吹きおろして来るからね」
「やあ、お早うございます」と、銀蔵は手拭の鉢巻を取って会釈した。「まったく朝晩は急に冬らしくなりましたよ。なにしろ十三夜を過ぎちゃあ遣り切れねえ。今朝なんぞはもう薄霜がおりたらしいからね」
「十三夜といやあ、あの晩にゃあ飛んだことがあったそうだね。私もたった今、御代官所の宮坂さんから詳しいことを聞いて来たんだが、働き盛りの若けえのが五人も一度にいぶされちゃあ堪まらねえ。刈り入れを眼のまえにひかえて、どこでも困るだろう。五人の墓はみんなこの寺内にあるんだね」
「そうですよ。先祖代々の墓がみんなこの寺内にあるんだからね。ところが、どうも困ったことが出来てね」
「なんだ。何が困るんだ」と、長次郎はそこに束《たば》ねてある枯れ枝の上に腰をおろした。
「小女郎がやっぱり悪戯《いたずら》をするらしい。毎晩のようにやって来て、五人の墓の前に立っている新らしい塔婆を片っぱしから引っこ抜いてしまうんですよ。花筒の樒《しきみ》の葉は掻きむしってしまう。どうにもこうにも手に負えねえ。初七日《しょなのか》を過ぎてまだ間もねえことだし、親類の人達だって誰が参詣に来ねえとも限らねえから、あまりこう散らかして置いてもよくねえと思って、毎朝わしが綺麗に直して置くと、毎晩|根《こん》よく掻っ散らして行く。こっちも根負けがしてしまって、きのうも佐兵衛どんの兄貴が来た時にその訳をよく話して、もうそのままに打っちゃって置くつもりですよ。けさはまだ行って見ねえが、きっとやっているに相違ねえ。小女郎もあんまり執念ぶけえ。五人の命まで奪ったら、もういい加減に堪忍してやればいいのに……。生霊《いきりょう》や死霊とは違って、あの小女郎ばかりは和尚様の回向《えこう》でも供養でも追っ付かねえ。ほんとうに困ったもんですよ」
「村の者はみんな小女郎の仕業と決めているんだね」
「まあ、そうですよ」と、銀蔵は手拭で洟《はな》をこすりながらうなずいた。「なにしろ子狐を責め殺したのが悪かったんですよ。死んだ者の親戚の人達もまあ仕方がねえと諦めていたんだが、その中でたった一人、今も云った佐兵衛どんの兄貴の善吉、あの男だけはまだそれを疑って、どうも狐の仕業じゃあるめえと云い張っているんだが、ほかにはなんにも証拠も手がかりもねえことだから、どうにもしようがねえ。どう考えても狐の仕業と決めてしまうよりほかはありますめえよ」
「そうさ。それにしても執念ぶかく墓をあらすのは良くねえな。なにしろ、その新ぼとけの墓というのを拝ましてくれねえか」
銀蔵に案内させて、長次郎は墓場の方へ行ってみると、かなりに広い墓場の入口に先ず六右衛門の墓場を見いだした。墓の前には新しい卒堵婆《そとば》が立っていた。樒の花筒がすこし傾いているのは昨夜の風の為であるらしく、何者にか掻き散らされた形跡も見えなかった。銀蔵は怪訝《けげん》な顔をして眼を見はった。
「はてね。けさは何ともなっていねえぞ」
彼はあわてて石塔のあいだを駈けまわって、更に次郎兵衛の墓の前に出ると、ここにも卒堵婆や花筒が行儀よく立っていた。それから順々に見てまわると、ほかの三人の墓の前にも今朝はなんの異状もなかった。
「こりゃあ、不思議だ。もう十日にもなるから、小女郎も堪忍してくれたかな」と、銀蔵はほっ[#「ほっ」に傍点]としたように云った。
「きのうの朝はみんな倒してあったんだね」
「塔婆も花筒もみんな打《ぶ》っ倒してあったのを、わしが一々立て直したんですよ」
「むむ」と、長次郎は新らしい卒堵婆の一本に手をかけて、明るい日のひかりに透かして視た。かれは更に自分の足もとを見まわしながら云った。「お前、以前はずいぶん綺麗好きだったが、だんだんに年を取ったせいか、この頃はあんまり掃除が届かねえようだね。きのうここらを掃かねえのかね」
「きのうは葬式《とむらい》で、茶を沸かすやら、火を起すやら、わし一人でなかなかここらの掃除までは手が廻らなかったからねえ」と、銀蔵は笑っていた。
長次郎は落葉を踏みわけて、五人の墓の卒堵婆を一々見てあるいた。中にはそれを引きぬいて、打ち返してじっと眺めているのもあった。かれは草履の爪さきでうず高い落葉を蹴散らしながら、墓のまわりの湿《しめ》った土の上をいつまでも見廻した。それが済んで引っ返そうとする時に、かれは隅の方に立っている小さい墓にふと眼をつけた。その前に立っている卒堵婆もあまり古いものではないらしく、花筒には野菊の新らしい花がたくさん生けてあった。長次郎は銀蔵を見かえって訊いた。
「あれはどこの墓だね」
「あれかね」と、銀蔵は伸び上がりながら指さした。「あれはおこよ坊の墓ですよ」
「花がたくさん供えてあるじゃねえか。おこよというのは、このあいだ身を投げた娘だろう。違うかね」
「そうですよ。可哀そうなことをしましたよ」
ふたりの足はおのずとその墓の前に立った。
「おこよの死んだのはいつだっけね」
「先月……ちょうど十五夜の晩でしたよ」
「十五夜か」と、長次郎はすこし考えていた。「一体あの娘《こ》はどうして死んだんだ。いい娘だったという噂だが……」
「川のふちへ芒《すすき》を取りに行って滑り込んだというんだがね。世間じゃあいろいろのことを云いふらす者もあって、何がなんだか判らねえ」
「どんなことを云い触らすんだね」
云いながら長次郎は身をかがめて、又もやその墓のまわりを身廻していた。
「仏に疵をつけるのはいけねえことだ」と、銀蔵は溜息をついた。「まして若けえ娘っ子に……。あんまり可哀そうで滅多なことは云われねえ」
かれは固く口をつぐんで、その以上のことは何にも云わなかった。長次郎は無理に訊き出そうともしなかった。銀蔵おやじの強情なことをよく知っている彼は、ここで無益の詮議をするよりも、おこよの死についてはほかに幾らも探索の道があると思ったので、そのままに聞き流してこの寺を出た。
三
「おや、親分さん。いらっしゃいませ」
茶店の女房は愛想《あいそ》よく長次郎を迎えた。茶店といっても、この村はずれに荒物屋と駄菓子屋とを兼ねている小さい休み茶屋で、店の狭い土間には古びた床几が一脚すえてあった。女房がすぐに持ち出して来た煙草盆と駄菓子の盆とを前に置いて、長次郎は温《ぬる》い番茶を一杯のんだ。店の前には大きい榎《えのき》が目じるしのように突っ立って、おあつらえ向きの日よけになっていた。時候の挨拶や、この出来秋《できあき》の噂などが済んで、長次郎はやがてこんなことを云い出した。
「ねえ、おかみさん。御用でおれは時々こっちへも廻って来るが、もともとこの村の落穂を拾っている雀でねえから、土地の様子はあんまりよく知らねえ。なんでも先月の十五夜の晩に、おこよといういい娘《こ》が川へ陥《はま》って死んだというじゃあねえか」
「ほんとうにあの娘は可哀そうなことをしましたよ」と、女房は俄かに眼をしばたいた。「村では評判の容貌《きりょう》好しで、おとなしい孝行者でしたが、十五夜の晩に芒《すすき》を取りに出たばっかりに、あんなことになってしまって……」
「十五夜は朝から判り切っているのに、日が暮れてから芒を取りに出るということもねえじゃねえか」と、長次郎はあざわらうように云った。「あの娘は幾つだったね」
「十九の厄年です」
「十九といえばもう子供じゃあねえ。お月さまの顔を拝んでから芒を取りに行くほどうっかり[#「うっかり」に傍点]してもいねえ筈だ。親孝行でも、おとなしくても、十九といえば娘盛りだ。おまけに評判の容貌好しというんだから、傍《はた》が打っちゃって置かねえだろう。あの娘が死んだのは、なんでもほかに訳があるんだと世間じゃあ専ら噂しているが、おかみさんは知らねえのかね」
「親分さんもそんな事をお聞き込みでしたか」と、女房は相手の顔をじっと見つめた。
「世間の口に戸は閉《た》てられねえ。粗相《そそう》で死んだのか、身を投げたのか、自然に人が知っているのさ。高巌寺でもそんなことを云っていたっけ」
「高巌寺で……。和尚様ですか、銀蔵さんですか」
「まあ、誰でもいい」と、長次郎はやはり笑っていた。「ねえ、おかみさんも知っているんだろう」
相手が御用聞きである上に、高巌寺から大抵のことを聞き出して来たらしいので、女房もうっかり釣り込まれて、訳も無しに長次郎の問いに落ちた。その話によると、おこよの死は不思議なことがその原因をなしているのであった。
おこよは四十を越えた盲目の母とふたりで貧しく暮らしている娘であった。水呑み百姓の父はとうに世を去って、今年十四になる妹娘のお竹は、四里ばかり距《はな》れたところに奉公に出ている。おこよは孝行者で、昼間は庄屋の茂右衛門の家へ台所働きに行って、夜は自分の家に帰って近所の人の賃仕事などをして、どうにか斯《こ》うにか片輪者の母を養っていたが、かれが容貌がいいのはここらでも評判であった。したがって、村の若い者どもから度々なぶられたり袖を曳かれたりしたこともあったが、おとなしい彼女は振り向いても見なかった。
そのうちに、かれの身の上に思いもよらない幸運が向いて来た。かれの孝行と容貌好しとが隣り村にもきこえたので、相当の家柄の百姓の家から嫁に貰いたいという相談を運んで来て、母も一緒に引き取って不自由させまいというのであった。その媒介人《なこうど》はかの高巌寺の住職で、話はもう半分以上まで進行したときに、今度は思いもよらない不運がかれの上に落ちかかって来た。それは実に飛んでもない話で、かれは彼《か》の小女郎狐と親しくしているという噂であった。
おこよは用の都合で暮れてから庄屋の家を出ることもあった。その帰り途で、彼女はここらにめずらしい寺小姓風の美少年に出逢って、暗い鎮守の森の奥や、ひと目のない麦畑のなかへ一緒に連れ立って行ったことがある。その美少年は小女郎狐か、もしくはその眷族の化身《けしん》で、かれは畜類とまじわっているのであるという奇怪の噂はだんだんに広まって来た。それが隣り村にもきこえたので、縁談は中途で行き悩みになった。さりとは途方もないことであると、高巌寺の住職はおどろいて怒って、その噂の主《ぬし》をしきりに詮議したが、確かにそれと取り留めたこともないうちに、折角の縁談はとうとう毀れてしまった。それから三日目の十五夜の晩に、おこよの死体は村ざかいの川しもに見いだされた。
若い美しい娘の死については何かの秘密がまつわっているであろうとは、長次郎も最初から大抵想像していたが、かれの運命もまた小女郎狐に呪《のろ》われていようとはさすがに思いも寄らなかった。
「なるほど飛んでもねえ話だ」と、長次郎も溜息をついた。「しかし隣り村の家というのもあんまり※[#「しんにょう+(山/而)」、第4水準2-89-92]《はや》まっているじゃねえか。ほかの事と違って、嘘かほんとうかよく詮議して見たらよかろうに、それですぐに破談にしてしまうというのは可哀そうだ。それがために容貌よしの孝行娘を殺してしまったんだね」
「ほんとうにむごたらしいことをしましたよ」と女房も鼻をつまらせた。「つまりあの娘《こ》の不運なんですよ。狐のことは嘘かほんとうか判りません。なにをいうにも相手が小女郎さんですから、どんなことをしないとも限りませんけれど……」
いずれにしても、おこよの死は悼《いた》ましいものであったと、女房はかれの不幸にひどく同情していた。そして、更にこんなことを付け加えて話した。おこよを嫁に貰おうとしたのは、となり村の平左衛門という百姓の家で、かれの夫となるべき平太郎という伜は小女郎狐の噂を絶対に否認して、是非ともおこよを自分の妻にしたいと云い張ったが、父の平左衛門は首をかしげた。むかし気質《かたぎ》の親類どもからも故障が出た。たといそれが嘘であろうとも、ほんとうであろうとも、仮りにもそんな忌《いま》わしい噂を立てられた女を迂濶《うかつ》に引き入れるということは世間の手前もある。ひいては家名にも疵がつく。嫁はあの女に限ったことではない。そういう多数の議論に圧し伏せられて、平太郎はよんどころなしに諦めてしまったが、内心はなかなか諦め切れないでいるところへ、おこよの水死の噂が伝わったので、それは芒を取りに行った為のあやまちではない、その死因はたしかに縁組の破談にあると彼は一途《いちず》に認定した。その以来、彼はなんだか物狂わしいような有様となって、ときどきには取り留めもないことを口走るので、家内の者も心配している。現に二、三日まえにも鎌を持ち出して、これから小女郎狐を退治にゆくと狂いまわるのを、大勢がようように抱き止めたというのであった。
「そうかえ」と、長次郎はまた溜息をついた。「そりゃあ困ったものだ。かさねがさねの災難だね」
「やっぱり小女郎さんが祟っているのかも知れません」と、女房は怖ろしそうにささやいた。「そればかりじゃありません。親分も御承知でしょうが、お庄屋さんの猪番小屋で五人も一緒に死ぬという、あれも唯事じゃありますまい」
云うときに店の前に餌を拾っている雀がおどろいたようにぱっ[#「ぱっ」に傍点]と起ったので、長次郎はふとそっちに眼をやると、大きい榎のかげから一人の男が忍ぶように出て行った。長次郎はそのうしろ影を頤《あご》で指しながら小声で女房に訊いた。
「あの男は誰だえ。村の者だろう」
「善吉さんのようです」と、女房は伸びあがりながら云った。「このあいだ、猪番小屋で死んだ佐兵衛さんの兄さんですよ」
「むむ、そうか」
長次郎はうなずきながらそっと店の先に出て、再び彼のうしろ姿を見送ると、善吉はなにか思案に耽っているらしく、俯向き勝ちにぼんやりと歩いて行った。うしろ姿から想像すると、かれはまだ二十四五の若い者であるらしかった。寺男の銀蔵おやじの話によると、かれは弟の横死を狐の仕業と信じていないという。――その話を長次郎は今更のように思い出した。
「おかみさん。どうもいつまでもおしゃべりしてしまった。だが、まあ気をつけねえ。お前のような年増盛りは、いつ小女郎に魅《み》こまれるかも知れねえ」
「ほほ、忌《いや》でございますよ。毎度ありがとうございました」
茶代を置いて、長次郎はそこを出た。この村にはほかに知っている家もないので、彼はもう一度代官の屋敷へ引っ返して、宮坂のところで午飯を食わせて貰って、それから遠くもない隣り村へ出かけて行った。平左衛門の家の近所へ行って、よそながら平太郎の噂を聞くと、彼がこのごろ少し物狂わしくなったのは事実で、この月初めから二、三度も家を飛び出したことがある。世間の聞えをはばかって親達はそれを秘密にしているが、自分の妻にと思い込んだ女が突然に悲惨の死を遂げると同時に、かれも取り乱して本性を失ったのは、近所でもみな知っているとのことであった。平太郎は今年|二十歳《はたち》で、ふだんがおとなしい男であるだけに、一時に赫《かっ》と取り詰めたのであろうという者もあったが、大体に於いてはやはり彼《か》の小女郎の仕業という説が勝を占めていた。小女郎さんが魅《み》こんでいる女を横取りして自分の女房にしようとしたので、その祟りで女は執り殺された。平太郎にも狐が乗り憑《うつ》って、あんな乱心の体たらくになったのであると、顔をしかめてささやくものが多かった。
乱心して時々に家を飛び出す男――すでに乱心している以上は何事と仕出《しで》かすか判らない。長次郎は更に平左衛門の家の作男《さくおとこ》をそっと呼び出して、主人の伜はこの十三夜の夜ふけに寝床をぬけ出して村境の川縁《かわべり》にさまよっていたのを、ようように見つけ出して連れ戻ったという事実を新らしく聞き出した。その家は成程ここらでも相当の旧家であるらしく、古い門の内には広い空地《あきち》があって、大きい柿の実の一面に色づいているのも何となく富裕にみえた。作男と話しながら、長次郎はときどき門の内を覗いていると、ひとりの若い男が何処からか不意にあらわれた。かれは跳りあがって長次郎の眼の前に突っ立った。
「さあ、一緒に来い。小女郎めを退治に行くから」
それが平太郎であることを長次郎はすぐに覚った。彼はつづいて叫んだ。
「小女郎ばかりでねえ。佐兵衛も六右衛門もみな殺してやる。あいつらは狐の廻し者だ。あと方もねえことを触れて歩きゃあがって、おれの女房を狐の餌食《えじき》にしてしまやがった」
長次郎は笑いながら彼の蒼ざめた顔をじっと眺めていた。
四
その晩、新石下の村でまた一つの事件が起った。かの善吉の妹のお徳が兄の寝酒を買いに出た帰り途に、田圃路《たんぼみち》で何者にか傷つけられた。善吉と佐兵衛とお徳とは三人の兄妹《きょうだい》で、かれはまだ十五の小娘であった。近ごろ中《なか》の兄を失って心さびしい彼女は、宵闇の田圃路を急ぎ足にたどって来ると、暗いなかから何者かが獣のように飛び出して来て、だしぬけに彼女の顔を掻きむしったので、お徳はきゃっ[#「きゃっ」に傍点]と悲鳴をあげて、手に持っていた徳利を捨てて逃げ出した。ようように家へころげ込んで母や兄に見て貰うと、かれは頬や頸筋をめちゃくちゃに引っ掻かれて、その爪あとには、生血《なまち》がにじみ出していた。
「狐の仕業《しわざ》だ。佐兵衛を殺したばかりでは気が済まねえで、今度は妹に祟ったのに相違ねえ」
こんな噂が又すぐに村じゅうにひろがった。これも寝酒を買いに出た高巌寺の銀蔵は、途中でその噂を聞いて急に薄気味悪くなって、どうしようかと路ばたに突っ立って思案していると、不意にその肩を叩く者があった。ぎょっ[#「ぎょっ」に傍点]として透かしてみると、頬かむりをした長次郎が暗い蔭に忍んでいた。
「おお、親分。お聞きでしたか、小女郎がまた何か悪さをしたそうで……」
「そんな話だ」と、長次郎はうなずいた。「ときにお前に無心がある。今夜はお前のところへ一と晩泊めてくれねえか」
耳に口を寄せてささやくと、銀蔵も幾たびかうなずいた。
「わかりました、判りました。さあ、すぐにお出でなせえ」
「お前、どっかへ行くんじゃあねえか」
「寝酒を一合買いに行こうと思ったんだが、まあ止《よ》しだ」
「酒はおれが買う。遠慮なく行って来ねえ」
「だが、まあ止そうよ」
「じいさんも狐が怖いか」と、長次郎は笑った。
「あんまり心持がよくねえ。おまけに今夜は闇だから」
銀蔵は長次郎と一緒に引っ返した。庫裏《くり》に隣った彼の狭い部屋に案内されて、長次郎は炉の前でしばらく世間話などをしていたが、やがて四ツ(午後十時)に近いころに、彼は再び手拭に顔をつつんで暗い墓場の奥へ忍んで行った。宵闇空には細かな糠星《ぬかぼし》が一面にかがやいて、そこらの草には夜露が深くおりていた。大きい石塔のかげに這いかがんで、長次郎はしずかに夜のふけるのを待っていると、そより[#「そより」に傍点]とも風の吹かない夜ではあったが、秋ももう半ばに近いこの頃の夜寒が身にしみて、鳴き弱った※[#「虫+車」、第3水準1-91-55]の声が悲しくきこえた。
半時あまりも息を殺していると、うしろの小さい丘を越えて、湿《しめ》った落葉を踏んで来るような足音がかさこそ[#「かさこそ」に傍点]と微かにひびいた。長次郎は耳を地につけて聞き澄ましていると、その小さい足音はだんだんにこちらへ近づいて、墓場の垣根をくぐって来るらしかった。垣根はほんの型ばかりに粗《あら》く結ってあるので、誰でも自由にくぐり込むことを長次郎は知っていた。星のひかりに透かしてみると、黒い小さい影は犬のように垣根をくぐって、一つの石塔の前に近寄ったかと思うと、その石塔の暗いかげからも又ひとつの黒い大きい影が突然あらわれた。
大きい影は飛びかかって、小さい影を捻じ伏せようとするらしかった。小さい影は振り放そうと争っているらしく、二つの影は無言で暗いなかに縺《もつ》れ合っていた。やがて小さい影が組み伏せられたらしいのを見たときに、長次郎も自分の隠れ家から飛び出して、まずその大きい影を捕えようとすると、彼はそこにある卒堵婆を引きぬいて滅多なぐりに打ち払った。その隙をうかがって小さい影は掻いくぐって逃げようとしたが、大きい影はその掴んだ手を容易にゆるめなかった。長次郎に卒堵婆を叩き落されて、大きい影がそこに引き据えられると同時に、小さい影も一緒に倒れた。袂から呼子の笛を探り出して、長次郎がふた声三声ふき立てると、それを合図に銀蔵が枯枝の大松明《おおたいまつ》をふり照らして駈け付けた。
松明の火に照らし出された二人の影の正体は、二十四五の大男と十四の小娘とであった。銀蔵は先ずおどろいて声をあげた。
「あれ、まあ、善吉どんにお竹っ子か」
男は佐兵衛の兄の善吉であった。娘はかのおこよの妹のお竹であった。自分の弟の松葉いぶしに逢ったのを小女郎狐の仕業と確信することの出来ない善吉は、その墓をあらす者をも併せて疑って、果たしてそれが狐であるか無いかを確かめるために、かれは誰にも知らさずに昨夜もこの墓場に潜んでいると、夜の明けるまで何者も忍んで来る形跡はなかった。きょうの午前《ひるまえ》に、かれが村はずれの休み茶屋を通りかかると、茶屋の女房が客を相手に小女郎狐の噂をしていた。それがふと耳にはいったので、彼は店さきの榎のかげに隠れて立ち聴きをしていると、隣り村の平太郎の噂が耳にはいった。それに就いては少し思い当ることもあるので、かれは松葉いぶしの下手人の疑いを平太郎の上に置いた。そうして弟の仇を取るために、その方面にむかって探索しようと決心していると、その宵には妹のお徳が何者にか傷つけられた。かさねがさねの禍《わざわ》いに彼はいよいよ焦燥《いらだ》って、もう一度その実否《じっぴ》をたしかめるために、今夜もこの寺内に忍び込んで、長次郎より一と足さきに墓場にかくれて、自分の弟の墓のかげに夜のふけるのを待っていたのであった。
さすがは商売人だけに、長次郎は足音をぬすむに馴れているので、善吉もそれには気がつかなかった。お竹の足音はすぐに判ったので、彼はその近寄るのを待ち受けて、とうとう彼女を取り押えた。しかしその曲者が十四の小娘であったのは、彼に取っても意外の事実であったらしく、善吉はいたずらに眼をみはって、松明の下にうずくまっているお竹の姿を見つめていた。
「お前はここへなにしに来た」と、長次郎は先ずお竹に訊いた。
「姉の墓まいりに……」
「そんならなぜ垣をくぐって来た」
「お寺の御門がもう閉まって居りましたから」と、お竹は小声ながらはっきりと答えた。
「むむ、子供のくせになかなか利口だな」と、長次郎は笑った。「よし、判った。それじゃあこっちへちょいと来い」
かれはお竹を弥五郎の墓の前に連れて行って、一本の新らしい卒堵婆をぬいて見せた。銀蔵もあとから付いて来て松明をかざした。
「おい、お竹。お前の手を出してみろ」
「はい」
何ごころなく差し出す彼女が右の手をぐっ[#「ぐっ」に傍点]と引っ掴んで、長次郎は卒堵婆の上に押し付けた。
「さあ、悪いことは出来ねえぞ。この塔婆にうすく残っている泥のあとを見ろ。泥のついた手でこの塔婆をつかんで引き抜いたから、指のあとがちゃんと付いている。どうも子供の手の痕らしいと思ったら、案の通りだ。てめえ、毎晩この墓場へ忍んで来て、塔婆を引っこ抜いたろう。花筒を掻っ散らしたろう。さあ、白状しろ。まだそればかりでねえ、てめえは庄屋の猪番小屋へ行って何をした」
お竹はだまって俯向いていた。
「さあ、素直に云え」と、長次郎は畳かけて云った。「手前はなんの訳で墓あらしをしたんだ。いや、まだほかにも証拠がある。この五人の墓のまわりに小さい足跡が付いていることも昼間のうちにちゃん[#「ちゃん」に傍点]と見て置いたんだぞ。いくら強情を張っても、墓あらしはもう手前と決まっているが、猪番小屋の方はどうだ。これも確かに手前だろう。さあ、神妙に申し立てろ。さもないと盲目のおふくろを代官所へ引き摺って行って水牢へ叩き込むが、いいか」
お竹はわっ[#「わっ」に傍点]と泣き出した。
「もう仕方がねえ。お前、おぼえのあることなら、親分さんの前で正直に云ってしまう方がよかろうぜ」と、銀蔵もそばからお竹に注意した。
長次郎はともかくも、善吉とお竹を庫裏の土間へ引っ立てて行った。そうして、だんだん吟味すると、善吉が墓場に忍んでいた仔細は前にもいう通りの簡単なものであったが、お竹がそこへ忍んで来たのには驚くべき事情がひそんでいた。庄屋の猪番小屋に松葉と青唐辛とを積み込んで、番人をあわせて五人の男をいぶし殺したのは彼女の仕業であった。小女郎狐の正体はことし十四の少女であった。
もう逃がれられないと覚悟したらしく、お竹は長次郎の前で何事も正直に申し立てた。かれは姉のかたきを取るために、男五人をむごたらしくいぶし殺したのであった。姉が変死の報らせを受け取って、かれは四里ほど離れている奉公先から暇を貰って帰ってくると、盲目《めくら》の母はただ悲嘆に沈んでいるばかりで、くわしい事情もよく判らなかったが、姉のおこよが縁組の破談から自殺を遂げたらしいことは、年のゆかない彼女にも想像された。そればかりでなく、かれは仏壇の奥から姉の書置を発見した。母は盲目でなんの気もつかなかったのであるが、お竹はすぐそれに眼をつけて、とりあえず開封してみると、それは姉から妹にあてたもので、おこよの死因は明白に記《しる》されてあった。
おこよが隣り村へ縁付くことになったのを妬《ねた》んで、今まで自分たちの恋のかなわなかった若い者どもが、隣り村へ行って途方もないことを云い触らした。それは彼女が小女郎狐と親しくしているという噂で、かれはもう狐の胤《たね》を宿しているとまで吹聴した。罪の深いこの流言が正直な人達をまどわして、かれらが目論《もくろ》んだ通りおこよの縁談は無残に破れてしまった。それを云い触らした発頭人《ほっとうにん》はかの七助をはじめとして、佐兵衛、次郎兵衛、六右衛門、弥五郎、甚太郎、権十の七人であった。おこよは自分の縁談の破れたのを悲しむよりも、人間の身として畜生と交わりをしたという途方もない事実を云い触らされたのを非常に恥じて怨《うら》んだ。おとなしい彼女は世間にもう顔向けができないように思って、その事実の有無《うむ》を弁解するよりも、いっそ死んだ方が優《まし》であると一途に思いつめた。彼女はその書置に七人のかたきの名を記して、姉の恨みを必ず晴らしてくれと妹に頼んで死んだ。
姉と違って勝ち気に生まれたお竹は、その書置を読まされて身も顫《ふる》うばかりに憤った。あられもない濡衣《ぬれぎぬ》をきせて、たった一人の姉を狂い死にさせた七人のかたきを唯そのままに置くまいと堅く決心したが、なにをいうにも相手はみな大の男である。ことし十四の小娘の腕ひとつで、容易にその復讐はおぼつかないので、しばらく忍んで時節を窺っているうちに、あたかもかの佐兵衛ら七人が十三夜の宵から猪番小屋にあつまったのを知って、かれは小屋の外にかくれて彼等の酔い倒れるのを待っていた。しかし自分の小腕で七人の男を刺し殺すことはむずかしいと思ったので、かれは俄かに松葉いぶしを思い立って、そこらから松葉や青唐辛をあつめて来て、七人のかたきを狐か狸のようにいぶしてしまった。
お竹はその足ですぐに代官所へ名乗って出るつもりであったが、母のことを思い出して又躊躇した。姉も自分もこの世を去っては、盲目の母を誰が養ってくれるであろう。それを思うと、かれは命が惜しくなった。一日でも生きられるだけは生き延びるのが親孝行であると思い直して、かれは人に覚られないのを幸いに自分の家に逃げて帰った。偶然に思いついた松葉いぶしが勿怪《もっけ》の仕合わせで、世間ではそれを狐の祟りと信じているらしいので、彼女はひそかに安心していたが、それでもまだなんだか不安にも思われるので、それが確かに狐の仕業であるということを裏書きするために、かれは更に高巌寺に忍んで行って、五人の墓をたびたびあらした。しかし五人の遺族のうちで、佐兵衛の兄だけは狐の仕業であるか無いかを疑っているという噂があるので、かれは飽くまで狐であることを信用させるために、暗い田圃のなかに待ち受けていて、善吉の妹をも傷つけた。相手の顔を掻きむしったのも、狐の仕業と思わせる一つの手だてであった。乱心の平太郎がこの事件になんの関係もないことは明白であった。
「わたしくが生きて居りませんと、片輪の母を養うものがございません。もう一つには仇のうちで五人は首尾よく仕留めましたが、二人は助かりました。その二人を仕留めませんでは、姉の位牌に申し訳がないと存じまして、今まで卑怯にかくれて居りました。それがためにいろいろ御手数をかけまして重々恐れ入りました」
お竹は悪びれずに申し立てた。
この捌きには、土地の役人共も頭を悩まして、例の「御伺」を江戸へ差し立てると、ひと月余りの後に「御差図書」が廻って来た。江戸の奉行所の断案によると、かの七人の者どもは重罪である。あと方もなき風説を云い触らして、それがためにおこよという女を殺したのは憎むべき所業である。殊に人間が畜生の交わりをしたなどというのは、人倫を紊《みだ》るの罪重々である。すでに死去したものは是非ないが、生き残った甚太郎と権十の二人には死罪を申し付くべしというのであった。
お竹は幼年の身として姉のかたきを討ったのは奇特《きどく》のことである。一切お咎めのない筈であるが、彼女はその罪跡を掩わんがために、墓場をあらしたのと、罪もないお徳の顔を掻きむしったのと、この二つの科《とが》によって所払いを申し付ける。しかし盲目の母を引き連れて流転《るてん》するのは難儀のことと察しられるから、村方一同はかれに代って母の一生を扶持すべしとあった。
これでこの一件も落着《らくぢゃく》した。人間の幸不幸は実にわからない。幸いにいぶし殺されるのを免かれた甚太郎と権十とは一旦入牢の上で、やがて死刑に行なわれた。
お竹は村を立ち退いて、水戸の城下へ再び奉公に出た。盲目の母は高巌寺に引き取られて村方から毎年何俵かの米を貰うことになった。その以来、この村では小女郎狐の噂も絶えてしまった。
底本:「時代推理小説 半七捕物帳(二)」光文社文庫、光文社
1986(昭和61)年3月20日初版1刷発行
入力:tatsuki
校正:菅野朋子
1999年9月25日公開
2004年2月29日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
| 12月20日 水 冬眠・飛ぶ夢・鍋 |
『兵庫県の六甲山で約3週間遭難し「焼き肉のたれで生き延びた」と伝えられた西宮市職員打越三敬さん(35)が19日退院し会見。遭難2日後の10月9日に意識を失い、31日に発見されるまで20日以上食べ物だけでなく、水すら飲んでいなかったことが分かった。会見に同席した医師は「体温が約22度という極度の低体温症だった。動物の冬眠に近かったのではないか。驚異的な生命力だ」と説明。保護時はほとんどの臓器が機能停止状態だったが、現在は後遺症を残さずに回復した。打越さんは10月7日に遭難。意識を失う前、試しに焼き肉のたれをなめたが「とても食べられたものじゃないと思った」と笑った。医師も、焼き肉のたれが命をつないだという家族の当初の説明を否定した。[2006年12月19日21時28分]日刊スポーツ』。――ま、マジですか!? それは人間としてはX−MENあるいはファンタスティック・フォーに参加できるほどの超常能力のはずだ。まあニュースの出所がソコなので、ちょっとアレな気もするのだが、事実だとすれば打越三敬さんを巡る各国人体低温保存研究者の熾烈な争奪戦などが起こるだろう。それほどえらいこっちゃな行為なのである、人間の冬眠という奴は。狸もぜひ身に付けたい能力のひとつだ。
『中国の鳥人』が妙に気に入ってしまい、またじっくり再見した。観れば観るほど、シナリオを少々補填すればさらに感涙必至の良作になるだろうと、狸内評価が上がってゆく。ただ、そのあたりの踏み込みの浅さもまた、やはり三池監督らしさではあるのだが。
そういえば自分も、飛ぶ夢を久しく見ない。狸の記憶に刻まれている数度の夢中飛行体験は、浮遊も飛翔も滑空もひたすら爽快で、目覚めた後まで気分が良かった。坂道を駆け下りながらどう弾みをつけると身ひとつで舞い上がれるか、どう風に乗れば上昇できるか、どんな呼吸で着地するか――そんな呼吸を体で覚えて行く過程を、今でも克明に体感として反芻できる。夢占いなどでは、飛ぶ夢というと欲求不満の現れとか、逆に物事がはかどる吉兆とか、例によってそれらしい解釈が占い者の数だけ並ぶわけだが、自分はそのときの現実生活などなんの関わりもなく、なんとなく時々気ままに飛んでいた気がする。今現在その夢を見にくいのは、実生活自体が根無しというか、浮き草状態だからなのだろう。そのうち力尽き地べたに張りついたら、また夢で飛べるのかもしれない。
穴の奥で明日食う餌の心配もなく冬眠しながら、夢の中では飛行狸と化して雪の山嶺に遊ぶ――至福だろうなあ。
ところで宮城産の生食用カキが1パック300円、これは安かったのだろうか。ふだん買ったことがないので、安いのか普通なのか判らないまま、やっぱりナマは怖い気がして、寄せ鍋パックに加えておいしくいただきました。総計690円のひとり鍋――おお、贅沢贅沢。
| 12月19日 火 カキとMP3 |
カキが食いたい。ノロウイルス騒ぎで、値が下がっているのだそうだ。そういえばニュースを観るごとに、二枚貝が危ない危ないと連呼していたので、いわゆる風評被害が出るのも当然か。実際はカキで患ったケースなど、今年は一件も確認されていないらしい。実際狸も、贅沢な生鮮魚介類などいっさい口にしなくとも、立派に罹患している。そもそもスーパーの食品売り場でオープン販売されているすべての食材や総菜、すべての外食、電車の中の空気、この時期みんな危険なのだ。今度スーパーに行って安かったら、ぜひカキを食おうと思う。カキの生食は狸の食性に無いから、当然土手鍋で――あ、そうか。体内の抗体が効いているうちに、生食も挑戦してみよう。
話変わって、久々に昔のMDプレーヤー(SONYの第1号機)を聴いて、あまりの潤いのある音に驚愕した。ここ半年、音楽はパソとMP3プレーヤーでばかり聴いていたが、同じ曲を初期のMDプレーヤーで聴いてみると、ボーカルの潤いがまるで別物。これはやっぱり圧縮の度合いの問題か――いや、それだと、そもそもMDだってアナログやCDに比べれば、しこたま圧縮されているはずだ。やはりソースそのもの以上に、ハードあるいは再生ソフトの違いだろう。たとえばパソで聴く時も、メディア・プレーヤーとリアル・プレーヤーを聞き比べれば、一長一短ながら明らかに音が違う。
そこでちょこっとネットを検索し、フリーソフトのプレーヤーなど試してみると――『Frieve Audio』に驚愕。MDほどではないが、ボーカルに潤いが戻る。詳細な理屈はまったく解らないが、これを使うとパソのサウンド・ボード付属のソフト設定などはいっさいキャンセルされてしまうようなので(メディア・プレーヤーやリアル・プレーヤーだと、そっちの設定も影響する)、きっと何か根本的な部分で、なんかいろいろ一所懸命やってくれているのだろう。そのかわり、かなりCPUのパワーを食うらしく、同時に立ち上げている他のソフトの反応は遅くなるが、じっくり聴くなら他のメジャーなプレーヤーなど敵ではない。
まあニュースにしてもMP3にしても、大勢に流されないのが、貧乏人の生きるツボ。
| 12月18日 月 大活字と絵買い |
書店でふと気づくと、しばらく新刊の文庫本から遠ざかっている間に、 ほとんどの文庫本の活字がいつのまにかでかくなり、行あたりの文字数も頁あたりの行数も、ずいぶん減っているようだ。昔から少ない原稿で一冊組まなければいけない場合や、老眼傾向の年配層狙いで活字を大きくすることはあったが、今はほとんどの新刊文庫が大活字化しているようで、その代わり厚さや価格も当然上昇傾向。めっきり近くが見えにくくなってきた狸などの目にたいへん優しい一方で、フトコロには厳しい。
昔の文庫本のイメージ、『ちっこい』『軽い』『安い』『ただし読みにくい』の内、今の文庫に残っているのは判型の小ささのみか。古い名作もルビやら仮名遣いやらでずいぶん読みやすく改版され、明治初期の作品など、原典にない段落分けや会話部分の改行まで、懇切丁寧に追加されているものまである。これでも活字離れは進む一方だと言うから、良い時代なのか悪い時代なのか、いよいよ解らない。
それでは、いわゆるラノベ系の文庫や新書の版組は――現物を確かめようと思ったら、地元の本屋では、コミック同様全冊ビニールで封印されてしまっているのであった。わはははは。もはや絵買い物件なのかしら。などと言いつつ結局自分で買ったのは、ほんまりう大先輩の『へるん幻視行』と、あさりよしとおさんの『まんがサイエンス』最新刊だったりする。なんのことはない。狸もまた新刊書読者としては、すっかり活字離れしてしまっているのであった。
まあ無理もない。昭和30年代前半に生まれた狸は、社会的にコミックの進化と共に成長して来ている。子供時代最初に憧れた職業は『マンガ家』で、その次は『なんでもいいから映画関係の人』だ。文章表現オンリー作品に目覚めたのは、せいぜい小学校高学年、思春期に突入してからか。そして最終的にそっちを自分の表現手法だと定めたとしても、見果てぬ憧憬は、やっぱり幼時の刷り込みにあるらしい。
| 12月17日 日 中国の鳥人→007 |
ケーブルで三池崇史監督の『中国の鳥人』を観る。いわゆる三池節にはもうまったくついていけない狸だが、原作が椎名誠さんなので、どんなもんかと観る気になったのである。予想どおり原作からは大筋を借りただけで、石橋蓮司さん演じるヤクザ(オリジナル・キャラ)にやはり三池節っぽさが窺え、初めの内は大いに危惧したが、後半それに慣れたら、あとはぐいぐいと引き込まれた。シナリオにあちこち穴はあるものの、未開へのロマンチシズムが、全体に一本の筋を通している。三池監督という方は、なんというかいわゆる職人監督としての手間仕事(今回はたぶんそんな企画のはずだ)だと、確かに手堅いのである。ところがいわゆる三池節に引き込めそうな題材となると、いっきに皮相的な軽量級お祭り騒ぎバイオレンス、そんな感じになってしまう。まあそこが大人気の由縁でもあろうが、狸としては条件反射的バイオレンスは、窮屈かつ退屈でたまらないのである。
裏番組の『007/リビング・デイライツ』も録画しており、続けて観てしまう。これはカットだらけの地上派放送で、過去劇場でもビデオでもDVDでも浴びるほど観た作品なので、早送りしながらの再確認。最新デジタル・リマスターとやらの画質は、さすがに良かった。それにしても――ああ、ティモシー・ダルトン様のジェームス・ボンド、ええわあ。ダニエル・クレイグの本編はまだ観ていないが、予告編から察する限り、ダルトンから野性的な部分のみ抽出、そんな印象だ。
中学校の頃からイアン・フレミングの原作を読んでいた007ファンとしては、誰がなんと言ってもダルトンがボンド役のトップである。次点がショーン・コネリーか。そんな適役なのに、シリーズ中最も興行的に恵まれない時期(ちょうどハリウッド・アクションが、一見リアル、しかし節操無用のなんでもありを尽くし始めた時代で、若いアクション・ファンの耳目が海綿状になってしまっていた)に当たってしまい、またその後なにやら版権問題で映画シリーズ制作自体が中断してしまったため、本作と次作の『消されたライセンス』の2本しか出演していないのが悔やまれる。作品的評価は今になって妥当な線まで高まっているようだが。
| 12月16日 土 自然の脅威 |
さて、自分も先週感染してしまったウィルス性胃腸炎、今年はノロ君中心に猖獗を極めているようで、いわゆる『腹風邪』が周囲の知人にも増えてきた。症状改善後も患者の便には一週間ほどウィルスが排出されると言うから、自分でもせいぜい外にバラまかないように気を使ってはいるのだが、自分の体内にできた抗体はそう長持ちしないという話だから、いざ再罹患しないよう注意しようとすると――ありゃりゃ、自分がなんぼ注意しても、完全な予防は不可能っぽい。
先週患った時だって、その前にナマモノなどいっさい口にしていないし、外食だって豚めしだの駅ソバだの、一応火の通ったものばかりだ。しかし仮に加熱した食物ばかり食ったとしても、口に入るまでにウィルスがほんのちょこっとくっついただけで、感染してしまうのである。どこぞのホテルでの集団感染のように、患者が吐いた後を知らずに歩いただけで移ってしまうこともある。しかしこの時期の都会で、あっちこっちの路上のコマモノが酔っぱらったコマモノかウィルス入りコマモノか、いちいち選別して対処するのは不可能なのではないか。加熱および塩素系消毒でしか死なないウィルスらしいから、すべての吐瀉物や便や手を過熱あるいは塩素系消毒すれば――無理やん。あるいはすべての食物を『嚥下直前に』過熱する――無理ですね。
なんのことはない、実際手洗いとうがいくらいしか個人的な予防手段はなく、いつ患ってもおかしくないのであった。畏るべし大自然の脅威、いや、超ちっこい自然の脅威。
| 12月15日 金 昇格 |
あー、また予算増えるぜ。海外派遣も『説明』だけでOKらしいぜ。誰が金出すんだろうなあ、って、俺らやんけ。ぶつぶつぶつ。
そういえば、昔、陸上自衛隊出身者に同窓会誌(?)のような雑誌を見せてもらったら、三菱重工の戦車の広告が載っており、『百発百中!』とかいうコピーに、大笑いしたことがあった。すみません三菱重工さん、金出すのはどっちかっつーと部外者の俺らなんですけど。いっそ自衛隊も民営化したらどうか。
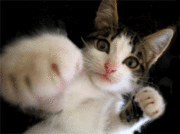 (拾いでスマソ)
(拾いでスマソ)
ところで三菱ふそうのリコール隠し裁判は、無罪で当然だろう。道義的疑問は確かに残る。岡本さんのご遺族のお怒りにも、重々うなずける。しかし客観的データを見る限り、法的な『有罪』の根拠は、皆無と言わざるをえない。今回の異常な三菱ふそうバッシングは、大政翼賛と同次元の、マスコミによるデータ無視情報(情動)操作、そんな気がする。
いわゆる『巨悪』の中には、売らんかなで世情を煽るマスコミも、当然含まれる。それにただ踊る感情的市民も、当然含まれる。
人も狸も猫も、現実社会の帳尻考えて踊りましょう。
 (また拾いでスマソ)
(また拾いでスマソ)
| 12月14日 木 生きる |
住基ネット違憲判決の竹中判事の自殺、無論あの判決を下すというとんでもない力業による精神的なストレスもあったのだろうが、本質的には「自分の出来ることはすべてやり尽くした。しかしあえてこの世のこれからを、これ以上見守りたくはない」、そんな『自決』に近い心境だったのではないかと思われる。竹中判事は、きっと日本や世界を、もう諦めざるを得なかったのだ。気持ちは解る、いや、解るような気がする。所詮国家・人類などというものは、一判事の良識によっても信念によっても自決によっても、小揺るぎもしない。
乾燥した空気に乗って、ほんの数個が人間の体内に入っただけで、その人間に吐きまくりや垂れ流しを強いるノロ・ウィルスにしたところで、せいぜい子供や老人など、弱者の命しか奪えない非力な存在だ。エボラ・ウィルスあたりは、いずれチンパンジーやゴリラが絶滅したら盛大に人類をシマツしてくれるという話だが、防壁とも言うべきそのチンパンやゴリラをせっせと減らしているのもまた人類に他ならず、やはり根本的に人類などというものは馬鹿であり、馬鹿につける薬はいまだに発見されていない。馬鹿は死ななきゃ治らないのである。
しかし、ハルマゲドンはない。そんなにあっさり白黒分別を迎えられるほど、人類の業《ごう》が浅いとは思われない。きっと人類と言う奴は最終的に、なんじゃやら頭でっかちのクリーンな意識体としてか、あるいはグロな汚染ミュータントとしてか、いずれにせよ客観的にはきわめてワビしい種の終末を、細々と迎えることになるだろう。
またしかし、案外その最後の時まで、おとめちっくなメルヘンが、存在しうるのではないか。
渺々たる砂漠――廃星の空に、グリーンの雲と、ピンクの雲が漂っている。
すでに本能も定かではなく無論生殖能力も失われているが、とにかく彼らは、その星に残った最後の意識体である。
グリーンの雲としては、その朝のピンクの雲の透け具合がなんだかとても好ましく思われ、ほよほよほよ、などと近寄って行ったりする。
ピンクの雲はちょっと警戒して、ほよほよほよ、などと遠ざかったりする。
しかしあんまり離れてしまうとなんだかとってもアレなので、まあ適度な間隔を保ちつつ、ほよほよ、ほよほよ。
あるいは悪臭を放つ泥濘とどす黒い岩礁――廃星の地平だか海だかなんだかよくわからない岩場を、土左衛門だかなんだかよくわからない三本腕の餓鬼のようなむくんだ生物が、のたのたと餌だかなんだかわからない海草のような物を抱えて、巣穴に帰ろうとしている。すると、波打ち際――もといヘドロ際で、水浴び――もといヘドロ浴びをしている、一本腕の痩せた餓鬼のような生物に出会う。
「ぎく」
「ぎく」
お互い、久方ぶりに出会う同類に警戒し、身をこわばらせるが、
――おお、あの崩れかけたほっぺたから覗く奥歯の歯並びが、とってもキュート。
――あらまあ、首の斜め横から生えている余分な腕が、とっても頼れそう。
どっちのアイデアでも、すでに生殖能力を失っているので、翌年あたり人類はめでたく滅亡してしまうのだけれど、まあ最後までラブラブである可能性も、生きている限り否定できまい。
| 12月13日 水 形と味 |
緑茶の輸出が増えているそうだ。日本食同様、欧米でも健康食品のイメージが定着しつつあるらしい。様々な加工食品(日本で言えば抹茶アイスのように、種々の料理に混ぜてしまう)にも使われるが、本来のお茶として喫される場合、どうも煮えくりかえったお湯を使ってしまい、緑茶の味も香りもあったものではない状態で、ありがたがられる場合が多いようだ。緑茶を紅茶と同じに扱っている訳である。
たまたま読んでいたキャサリン・サンソムさんの『東京に暮らす』(岩波文庫。昭和初期の英国外交官夫人の日本生活記。とてもおもしろい)に、まったく同じ、いや、逆の記述が出てきて、笑ってしまった。日本人の使用人は、気心さえ通じれば世界一正直で上等だが、紅茶の淹れ方だけは何十遍教えても理解できず、自分で淹れなければならない、そんな記述である。理解できないと言うより、そもそも紅茶が自分の食性に含まれていないので、「お茶と言うものにそんな煮えくりかえったお湯は絶対不可」と、ただ信じているだけなのだろう。実際その両方の淹れ方で飲み比べさせても、緑茶と同じように淹れた紅茶を、旨いと言うのではなかろうか。淹れる現場を見せない目隠しテストでも、案外その「茶葉の味への不慣れ」から、やっぱりそっちを旨いと言うかもしれない。
『敬愛なるベートーベン』などというタイトルの映画があるらしい。狸は寡聞にして「敬愛なる」という表現を、北の非漢字国家が♪ぴー♪の首領様をアヤシゲな和文でドッコイショするときの誤用としてしか知らない。このまま日本語として根付いてしまったりしたら、またひとつ「不快な新用例」が増えてしまうなあ。ちなみに「親愛なる」があるんだから良いんじゃないの、などという意見、あるいは「親愛なる」もおかしいんじゃないの、などという意見があるらしいのにも、困ってしまった。
どうも漢字や熟語というものを、非漢字国家の方々同様、表音文字として感覚的に扱うケースが増えているようだが、第一印象からの思いつきっぱなしじゃなくて、なるべく意味まで考えてみたほうがいい。本来、表意文字としての味があるんですから。
| 12月12日 火 硫黄島からの手紙(一部ネタバレ注意) |
『硫黄島からの手紙』を観た。超重量級の映画だった。『父親たちの星条旗』よりもストレートな戦場物で、泣きもこけおどしも排除した、理性による戦争映画である。渡辺謙さんもいいが、二宮和也という若手が思いがけず良かった。当初、いかにも当世若者風の口調に「ありゃ、やはりイーストウッドにもこうした日本語ニュアンスは演出不能か」などと心配してしまったが、時を追うごとに役柄の個性として成立して行き、ラスト近くではもう夢中になって「頑張れ横町のパン屋!! お前だけは生きて帰れ!! あのちょっとトロそうなでもかーいい奥さん、子連れ未亡人にしちゃマズイだろ!! どっか隠れてろ!! 俺が許す!!」などと、手に汗握って応援しているのであった。ラストで米国負傷者と共に並んでいる彼の微笑の、なんいうかあまりにも『普通の生活者』らしい無力さ清々しさ、この映画のテーマにおいては、謙さんの名演も越えたと言っていいだろう。ところで心配していた獅童さんは、やっぱりいつもの獅童さん以外の何者でもなく、しかし役柄自体がベタであるべき役だったため、今回は無事マッチング。
風俗細部・歴史的空気感には、どうしても異国的な違和感を覚えてしまう部分もあるのだけれど、それでも監督が米国人であることを思えば驚嘆に値する作り込みで、実際この前沈んだYAMATOなどよりははるかにリアル。事物を把握・類推する視線そのものに、老練な『理知による含羞』が宿っているからだろう。イーストウッドの本質は、昔からそこにある。『ダーティ・ハリー』の昔から、彼は闇雲にマグナムぶっ放して悪党ぶっ殺していたわけではない。人は個人として何を為すべきなのか、何を為してはならないのか、いつもそんな視線で『生活』していたのだ。
| 12月11日 月 ノーブレス・オブリージュ |
紀行番組で片っ端から鉄道が廃線になり過疎化し滅びてゆく僻村の姿に心が痛む一方で、その録画を見終わりたまたまリアルタイムの深夜番組が映ると、ヤラセか事実かは知らないが、ろくに日本語も学習していないイケメンとやらのガキ(月収500万のホストなのだそうだ)相手に、ひと晩で何百万も費やす小娘(23歳で無職だが金はなんぼでも家にあるのだそうだ)がフヤけた幼児語を発している。まあそれぞれ悪事をはたらいているわけではないから一種のイロモノのイキモノとしてほっとくとして、やはりこれは社会的に真の『階層意識』教育をもっと徹底せねばならんなあ、と強く思う。
たとえば鉄道だって、グリーン車や特別席の運賃を、もっと豪快に上げてしまえばいいのである。誰も乗らないかと言うと、そんなことはない。きちんとCM・ニュース等で情報操作すれば、馬鹿な成金は老若男女問わず、きちんと「私はセレブ」と乗ってくるし、真のセレブは当然セレブの存在意義として乗らなければならない。旧国鉄時代など、組合闘争にかまかけてなんでもかんでも平均化ばかり目指していたから山のような赤字が累積したのであって、民営化したからといって倒産間際の会社同様に不採算部門の整理ばかりやっていたのでは、公共事業まで数字転がしの場になってしまう(もうなってるか)。富の偏在が問題なのだから、末端の赤字解消など、さほど気にする必要はない。あるところから回してやればいいだけの話だ。あるところの間でだけ転がして「でも総合的には上向きです」などとたわけているから、末端が壊死していくばかりになる。
まあ「パンが無ければお菓子を食べればいいじゃない」はマリーアントワネットの言葉ではないらしいが、せっかく実際そんな意識に近い人間の氾濫するこの飽食の国なのだから、高いお菓子を食える方々にはせっせと食ってもらって、しかしそのお代金は、下々のパンに回す工夫をしていただきたい。しかし――どうもそれらの社会構造を担う国家中枢自体が、「パンが無ければお菓子を食べればいいじゃない」的生活感覚なのではないかと、近頃正直怖くなる。支配層のノーブレス・マラード化による、帝国崩壊への道だ。そうなってしまえば、大ローマ1000年帝国ですら崩壊する。
狸の父親世代には圧倒的不評を誇る、昔の池田首相の蔵相時代の失言「貧乏人は麦を食え」だが、確かに政治家の公的発言としてはイタいのだけれど、人間のホンネとしては、極めてまっとうだった気がする。もっともあれも実際の発言は、「所得に応じて、所得の少い人は麦を多く食う、所得の多い人は米を食うというような、経済の原則に副ったほうへ持って行きたいというのが、私の念願であります。」だそうだし、池田首相本人も、麦飯育ちだったそうだ。
ちなみに現在は麦の方がずっと高価だし、もともと栄養価も高い穀物だが。
| 12月10日 日 馬鹿の復活 |
昨夜はなぜかまた熱が上がって、ありゃ、また排便人生に逆戻りかと早めにフテ寝したら、ウィルス君たちのサヨナラ打ち上げパーティーだったらしく、本日は頭も腹もすっかり軽い。ただし、三日間カロリーメイトとコーンポタージュとパンと牛乳と野菜ジュースで過ごしたためか、腹は軽いが脚は重い。しかし病毒による脚の重さとシャリバテによる脚の重さは、「持ち上げよう」という気力において雲泥の差がある。ここはやっぱし卵とバナナ、などと重い脚を引きずり街に出て、ふと気づくと回転寿司屋のカウンターに座っている私はやっぱりお利口さんですか? だってさすがにナマモノは避け、出汁巻き卵とかお稲荷さんとか、きちんとよーく噛んで食べましたもん。ビールだって、モノホンじゃなくただのビアテイスト飲料ですもん。まあ明日はまたちょっと動かねばならないし、どうせ我が人生、もはや気力だけの問題なのである。不治の病の方々だって一所懸命生きている世の中、太った狸がいつまでも病気気分でいてはお天道様に申し訳が立つまい。……言い訳になっとらんがな。
ケーブルで、ハリウッド版の『シャル・ウィ・ダンス?』を観る。とても良い映画であった。しかしそれはあくまで古典的ハリウッド映画の良さ、つまり完全パッケージ娯楽商品・夢物語としての良さであって、「うん、座布団1枚!」くらいのスタンダードな快感である。周防監督のオリジナルの方は、リアルな知性の上に構築された花も実もある絵空事、そんな感じで、「おーい山田君、座布団2枚!」、そんな感じだったが。
体調が復活すると、笑えるニュースも目につく。『福島県いわき市内の小学校で、20代後半の男性講師がドッジボールのクラブ活動中、顔にボールが当ったことに腹を立て、ボールを投げた小学4年の男子児童を引きずるなどして背中や足にけがをさせていたことが9日分かった。同市教育委員会学校教育課によると、この講師は5日午後3時ごろ、昨年度から勤務している小学校の校庭で、3、4年生の児童とクラブ活動のドッジボールをしていた。児童の一人が投げたボールが顔に強く当たったため、かっとなってこの児童を引きずり、頭を平手でたたいた。児童は引きずられた際、背中や足にすり傷を負った。同校の校長と講師は6日に児童宅を訪ねて謝罪し、7日に同市教委に事件を報告した。8日には保護者説明会を開いて経過を伝え、謝罪した。児童は6日に学校を休んだものの、7日には登校した。同校はこの講師に6日以降、授業をさせていないという。同課は「講師本人からまだ話を聞いていない」としており、事情聴取後に対応を検討する。【田中英雄】(毎日新聞)12月10日19時24分更新』。わはははははは、いや、引きずられた子供には気の毒だが、なにやら未成年犯罪にも厳罰化をなどと言いつつ大人は相変わらず野放しのこの平等国家においては、もはや子供も大人に子供同士なみの気遣いをもって接してやらないと、どーゆー反応が返ってくるか判らないのである。
しかし一方で、死者と生者の不平等だけは、相変わらず顕著だ。『北海道南幌町で女子中学生が死亡した交通事故をめぐる札幌高裁での刑事裁判で、被害者の両親が一審と同様に法廷で遺骨を抱いて傍聴したいと申請したところ、同高裁が認められないと回答していたことが十日、分かった。遺族は「どうして認められないのか。当事者の美紗が法廷に入れないのはおかしい」として、同高裁に理由の説明を求める上申書を提出、回答を待っている。事故で亡くなったのは白倉美紗さん=当時(14)=。二○○三年九月、自転車に乗っていた美紗さんがトラックにはねられ死亡。一審の札幌地裁岩見沢支部では元トラック運転手の男に禁固三年、執行猶予五年(求刑禁固三年)の判決が言い渡されたが、検察側が控訴。十九日に札幌高裁で初公判が開かれる。遺影、遺骨などを抱いての傍聴を許可するかどうかなどは、通常裁判を担当する裁判官が判断し、許可されるかどうかは裁判によって異なる。父親の博幸さん(35)は「美紗に裁判を聞かせてあげたい」と話している。(中国新聞ニュース
)06/12/10』。これはおかしい。その事故の状況いかんに関わらず、赤の他人でも傍聴できる公判の席で、まして陪審員の感情的反応も判決に影響しないこの国で、当事者の一部がそこにいて不都合なはずはない。きっとその裁判官は、極度に鈍感か極度に鋭敏か、いずれにせよ己の公平感覚に自信がないのだろう。
| 12月09日 土 ぐたぐた |
寝床とトイレを往復する人生からなんとか立ち直ったためか、本日はぐっすり眠れたのだが、その夢見があまりに甘美かつ悲愴であった。過去にふられた女性たちが、昔のままの姿で、入れ替わり立ち替わり登場する。老舗の温泉らしい広々とした夜の岩風呂から、なにやらゴージャスナな王宮風の寝台まで、つまりきわめて着衣の少ない状態で、なにか時の経過を思わせる哀切な視線ながらも、「うっふん、昔に戻りましょうよ」の体勢らしいのだ。当然自分はめろめろと溶解し、なつかしく接触しようとするが――おお、なんということだ。自分だけはしっかり現状の中年肉体、つまり狸腹の赤ヘソではないか。陰毛もすでに白髪まじりだ。さらに病気で体力が落ちているせいか――立たない。
この歳になってしまうと、何か患って薬もらって思いきり寝てケロリ、というのは、よほど効果のあるワクチンやら抗生物質やらが存在する病原体相手でないと、なかなか難しそうだ。ウィルス性胃腸炎などというものは、いわゆる対症療法で辛さを抑えながら、根本的には自前の抗体による自然治癒を待つしかないのだろう。少なくとも今回もらえた薬は、みんなその手の薬剤だ。おかげさまで高熱やとんでもねー噴出は治まったものの、微熱はまだ続いているし、シモの物件も、ほんの少しずつ液体から物体に変化しつつある、そんな感じだ。まあ、便意がだいぶこらえられるようになったので、さほど生きるのが辛くはないが。
つくづく哀しいのは、冷蔵庫にある消費期限切れ食品である。昨日で切れたもの、本日切れるもの、どちらもとても今日明日に食えるような腹具合ではない。いつもなら三日や四日期限が過ぎても平気で食ってしまうが、さすがに今回は用心したい。ああ、肉まんがカレーまんが。餃子が焼売が。まあみんな97円均一商品とはいえ、やはり断腸の思いである。
しかしこんな状態でもくだらん話をよう打つよなあ俺、などと思いつつ、ほとんど10打に1打はキーを間違えている。やはり人間、アタマよりハラが大事なのだ。
| 12月08日 金 のたのた(下ネタ反転多し) |
二十四時間内にトイレ(大)に立った回数では、おそらく我が人生で最多を記録しただろう。情けない話だが、こらえきれずブリーフを2枚ほど汚してしまい、いっそ母親より先に紙おむつ人生に突入してしまいたいと思った。この時期、トイレも寒いのである。吐き気があるので缶入りカロリーメイト(あまり世間で人気はないようだが、実は病時の狸の好物でもある)くらいしか食えず、食ってしばらくすると、ほとんどそのまんまの形状の液体が、尻から噴出してしまう。
たかがウィルス性胃腸炎でも、小児や老人で時々死んでしまう人がいるのは、もちろん体力的な要因もあろうが、「こんなふうに排便中心で人生続けるよりは、いっそ早めにリタイアしてしまった方が楽なのではないか。まだちょっとしか生きてないから未練も少ないし」「こんなふうに残り少ない人生をトイレやオムツに費やすよりは、いっそ早めに成仏してしまったほうがラクなのではないか」、そうしたニュアンスの精神的要因も多いのではないか。
幸い午後遅くには、吐き気も治まり熱も下がり下のほうもいきなり噴出しようとするほどではなくなり、なんとか人生再開可能になったが、それでも便意は頻繁に襲ってくる。出る物も相変わらずカロリーメイト状で、ほんの少し色や質感が濃くなった程度だ。しかし「下痢が治まるまで2日、完治まで4日、ま、そんなとこかな」、そんなバンカラな医者の言葉を信じて、たくましく、ただしトイレの近所で生き続けようと思う。
| 12月07日 木 バテ |
明け方寝る前にはまったく正常だったのに、午前中寝床の中で突然吐き気に襲われ、幸い消化器内容物は腸までおりていたらしく寝床にぶちまけはしなかったものの、今度は下から噴出しようとするので慌ててトイレに立ったら、足腰がぎしぎしと軋んで痛い。トイレでのたうちまわりながら熱を計ったら、38度。頭まで痛くなってきた。
そろそろインフルエンザの予防注射しようと思っていたのに先を越されてしまったか、と思ったら、のたくりこんだ医院では、ウィルス性の胃腸炎らしいとのこと。流行っているのだそうだ。近頃良く聞くノロウィルスも、ご近所で集団感染が出たらしい。贅沢に生カキなど食べた記憶はないが、どうもあのウィルスは、状況によっては防ぎようがないらしい。まあ死ぬような病気ではないが、とにかく腹がむかむかして、風邪で寝ている時のような一種の退嬰的快感がないのはつらい。
| 12月06日 水 赤へそと釜飯 |
へそが赤くなって痛い。奥部でなく外周内側が、かぶれているようだ。貧窮しても風呂だけは相変わらず毎日入っているので、けして不潔なわけではないはずなのだが、これはもしや、アレなのだろうか。生涯で最も太っていた小学校高学年の頃、内股に頻発した――言いたくはないが――股ズレ、その仲間。つまり腹が膨らみすぎて、へそに刺激が増えてしまったとか。
小学校の頃は全身くまなく肥大化しており、特にへそに刺激は集中せず、それでも子供のこと一日中どたばた活動しているから、内股に最も摩擦が生じる。しかし今はへそを中心として胴体のみ肥大化しており、かつ座っている時間が多いので、シワやらベルトやらジャージのゴムやら、へそに最も負担がかかる。
とりあえず消毒薬を塗って、キティちゃんのバンドエイド(ヤフオクで落札した詰め合わせに入っていた奴)を貼ろうとしたら、狸腹のへそという奴は案外外周がでかくて、普通のパッドだとはみだしてしまう。ダイソーあたりで、でかいのも売っているだろうか。
ああ、腹を縮めたいなあ、と思いつつ、100円の釜飯の素と1本50円の焼き鳥を2本をぶっこんだ2合飯、一日こんなのを食っていても、日々腹は着実に膨らんでゆく飽食の中年狸なのであった、ぽこぽん、と。
ところで渡辺氏からのご指摘によると、昔の給食に出ていたのは、『鯨カツ』ではなく『鯨の竜田揚げ』らしい。いずれにせよ、山形市立第一小学校で昭和30年代末期の給食に出ていなかったことだけは確かだ。
| 12月05日 火 まあ散るわけにも行かないんだろうが |
なんかいろいろの帰りにレンタル屋に寄り、ふと、アダルト・コーナーのカーテンをくぐってみた。近頃はめっきりそっち関係の欲求は衰えてしまったので、あくまで現代の風俗把握目的である(ほんとよ)。で、メマイがした。棚に立ち並ぶ幾千のモデルさんのご尊顔、もののみごとに同じような化粧で同じような染髪で同じようなカットで、ほとんど見分けがつかない。まるでX星のレンタル屋に紛れ込んでしまったかのようだ。まあレンタル・ビデオ勃興期のように、類人猿に近い女性からピンク映画界の楚々とした美女まで取りそろえてくださいとは言わないが、確かにツブが揃って容姿の偏差値も高いにせよ、こう似たような女性の似たようなシチュエーションばかりだと、正直、萎える。ちっこくてずっこくて胸が小さくてでもおしりはちょっと大きめで、なんぼなんでも三つ編みにはもう無理があるけれども古風なセーラー服がまだなんとか似合いそうなおへちゃ顔のモデルさんのアナルが見てみたい(おい)、そんな男はもういないのだろうか。あるいは、やはり供給側が安全パイを狙っているだけか。結局アダルトDVDは借りず(ほんとよ)、『決戦! 南海の大怪獣』だの『田園に死す』だのを借りてくる。
ソニーのデジカメの修理が、もう仕上がってきた。昨年来の不良CCD騒動で、最近無償修理対象に追加された機種である。その件を知ったのもミクシィの渡辺氏の日記からで、知らなければ対象外として諦めていたわけだから、やはりネットという奴はありがたい。それにしても、先月30日に集荷してもらって本日届いてしまうというのは、異様に早い。ソニーも近年不手際続きだから、信頼回復に必死なのだろう。なんのかんの言われつつ、『U−50』のようなオリジナリティーに富んだデジカメを出してくれる会社なので、いまだに贔屓してしまう。でもソニーも昨年あたりから、すっかりラインナップがありふれた外観・仕様になってきた。守りに入ってジリ貧化するよりは、いっそ華々しく散ってほしい会社なんだがなあ。
| 12月04日 月 まあ人様々なんだろうが |
ネット上、応募原稿に関する情報源としての有名どころに、『下読みの鉄人』なる自称編集者の方のページと、『草一屋』という厳然たる新人賞出身プロ作家のページがあり、読み比べてみるととても面白い。とにかく意見が食い違うのである。総合的には『草一屋』のほうが、さすがはプロ作家だけあって、情報にリアリティーがある。一方『下読みの鉄人』のほうは、どうもフカシらしい部分や物理的に不可能な記述が散見され、これはもしや聞きかじりのアレではないのか、などと首をひねってしまう。本当に編集関係の方がやっているとしたら、なるほどそれで『おもしろい』小説より『あたりさわりがない』小説がたくさん世に出るのかと納得できる。
先日偶然見たテレビのバラエティーで、昔の学校給食(いわゆる昭和レトロの頃の)が取り上げられており、『脱脂粉乳』のまずさ、『鯨カツ』の美味しさ、『揚げパン』の嬉しさ、そのあたりが例によって話題の中心になっていた。懐かしくうなずきながら見た――のでは全然ない。自分も小学二年まであのララ物資だかユニセフ寄付だかの『脱脂粉乳』(アメリカでは家畜の飼料にも使われたとか)を飲まされたクチだが、けっこう旨かったと思う。大袈裟に「不味い不味い」と悶絶する級友も多かったのは確かだが、それでも過半数は黙って飲んでいたし、自分のように家畜なみに喜んで飲んでいた仲間も多かった。で、『鯨カツ』などという結構なシロモノを、給食でいただいた記憶はない。自宅で食べることはあったが、給食だと、魚肉ソーセージを1センチ厚くらいの輪切りにして三切れほど串に刺してフライにした『月見カツ』というのが、最上等のカツ物件だった。そして『揚げパン』となると、最近コンビニなどに復刻物件として並んでから、初めて口にした形態である。食パンの耳をただ揚げただけの奴は自宅でおやつに出たが、コッペパンまるごと贅沢に揚げてしまうなどという発想は、当時の山形の田舎にはなかったのだろう。
久しぶりに『食パンのてんぷら』を食いたくなった。給食で残ったパサパサの食パン(市販の食パンとちがい、まさに粉の味だけの奴)は、蒸し器で温めてもいいが、小麦粉に砂糖を入れた衣をつけて揚げると、最高のおやつになった。もっとも今の市販の食パンでやってしまうと、もとが柔らかくて甘みもあるので、かなりクドそうな気がする。
| 12月03日 日 まあ好き好きなんだろうが |
A4用紙横使用、縦組みで印字――まあ、ここまではほぼ全社同じだ(いや、ごく一部にひねくれ者はいるが)。しかし、同じ用紙を同じように使っても、文字数はお任せから30×30のパラパラから40×40のギッシリまで千差万別、用紙の綴じ方も、ただ「綴じろ」とだけ言う会社、なんにも言わない会社、何百枚あろうがただ「クリップで綴じろ」と言う会社――どうも、人間のコミュニケーションを扱うはずの部署としては、かなりアレな雰囲気が漂うところですね、各募集係というところは。
それ以上に不安を感じるのが、なんかものすごく面白くて個性的な作品を探し求めているはずのところが実際出版している作品は、かなりの割合で面白くも個性的でもない、そんな事実である。いや、いわゆる『読み捨て』の作品にも多大な需要があることは、かつて昼飯時の食堂で慌ただしく定食かっくらいながらなんかいろいろ読み飛ばしたり、疲れ果てて帰宅する電車の中の1時間をいかに疲れずにエンタメさせていただけるかでキオスクの文庫本を選別していたこともある自分としては、良くわかる。しかし、実際誰がどう見てもありふれてつまらない、そして実際ちっとも売れない作品も、日々きちんきちんと出版され続けているのは、やはり疑問だ。そのぶんを、かたっぱしから新人賞の三次落ちや最終選考落ち作品にでも回したほうが、よほど読者側は『面白い作品』を多く読めるのではないか。実際巷のベスト・セラー作品には、別の作品でデビューした方による過去どこかで落っこちた作品、そんなケースも多々あるわけで。
などといろいろ愚痴りつつ、最終選考にも残れない身としては、30×30で印刷してると紙代かかってしょうがないよなあ。ぶつぶつぶつ。せめて編集の方だけにでも、いっとき楽しんでいただきたいものである。ところで260枚のプリントアウトって、超特大クリップいっき挟みでもいいんでしょうかね。
あと、ワープロ原稿限定という規定も最近多いようなんですが、どんな面白い作品でも手書き原稿用紙だといきなりゴミにされちゃうんですかね。
| 12月02日 土 かけそば |
ザルやモリとは違い、かけそばの麺はほとんど奢る必要がないのに気づいた。こだわりの『とびきりそば』だろうが『八割蕎麦』だろうが特売品だろうが、あったかい汁がなみなみとかかってしまえば、食べる快感はさほど変わらない。さすがに最安価の乾蕎麦はコシがなさすぎてアウトだが、もういっこ上の乾蕎麦だと、下手に蕎麦粉の香りがしないだけかえって安い汁に合う。江戸時代、モリが正式でカケは下賎な食い方とされていたのは、どんな蕎麦でも同じような風味になってしまう、そんな理由なのだろう。貧乏人の冬越しには、ありがたい発見だった。
十数年前に『一杯のかけそば』という童話が話題になった時、「そんなビンボなら家族で食堂に行ってわざわざ一杯を分け合ったりしないで、自宅で乾麺でも湯がけば腹一杯食えるだろ」、そんなツッコミがあった。まあその話の場合は、そこの食堂の蕎麦が貧しい母子家庭にとっては亡くなった父親の思い出の味である、そんな設定があるわけで、人間貧窮しても過去の思い出はやっぱり大切なのだが、ならばその母子にはまだまだ精神的余裕があったのであり、あくまで豊かな国のシヤワセな童話なのである。『一杯のかけそば』の作者は、のちに大酒飲みの寸借詐欺常習者だったのがバレてしまいブタバコに入ってしまったが、それとてやはり豊かな国の、シヤワセな後日譚なのである。
世の中には、一杯のかけそばにもありつけずこときれるマッチ売りの少女のお仲間が、まだまだ実在するのだ。
| 12月01日 金 みんな死ぬまで生きている |
夕方買い物に出て仰天した。この寒空に、パチンコ屋の前で半裸のおねいさんがふたり、客を呼んでいる。一応羽織状のボアを纏ってはいるが、中身はきっちり水着状で、特に下半身はクイコミも寒々としたスケベ水着状だ。こんな雑多な街で過酷な営業やってるくらいだから、二流三流のイベント・ギャルさんかと思いきや、ちちもしりもいいし、ご尊顔もけして月並みではない。そういえば一昨年あたりも、同じような光景に遭遇したなあ。やっぱりこの国の景気は、相変わらずキビシイのである。
駅前のテナント・ビルでたかちゃんが出現し、勝手に走り回り始めた。なにやら掃除婦のおばさんの装備に興味を覚えたらしい。半裸のギャルではなく掃除婦のおばさんというところがいかにもたかちゃんらしいので、しばし挙動を観察させてもらう。
応募の締め切りまではまだひと月あるのだが、死美人物件の四度目の推敲が終わった。もはやこれ以上いじくる気力もないので、アマチュア作品としては、今度こそ最終稿になるのだろう。しかし応募要項によると、今回の梗概は、なんとたったの800字ででっちあげねばならない。前回新潮の応募時は2000字で、それでも四苦八苦したのである。元原は180000字以上あるのだ。この世から『梗概』という二文字を抹消してしまいたい。
音楽家の宮内國郎氏も、27日に死去されていたらしい。ウルトラ関係の音楽、ありがとうございました。合掌。